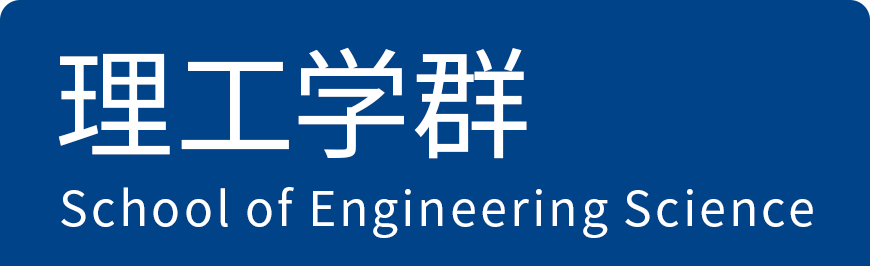
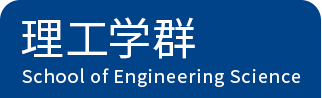


学生がそして教員が、高知にいながらにして、サイエンス、テクノロジー、そして人文諸科学の世界の最前線を、その最前線を開拓している第一線の研究者本人から聴くための、学群コロキウム「理工学のフロンティア」。豪華な講師陣が、直接、語りかけます。
| 講演回 | 講演者 | 講演タイトル | 日時/場所 |
|---|---|---|---|
| 第16回 | 近藤 寿人 博士 (大阪大学・名誉教授/JT生命誌研究館・顧問・表現ディレクター) |
iPS細胞を生み出す仕組みと転写因子SOX2の力 | 2026/2/6 14:40–16:10 B107教室 |
| 大人の組織の細胞に4種の転写因子を作用させると、胚発生初期の細胞に近いiPS細胞を生み出せます。このことを示した山中伸弥氏たちの研究成果から、正常の発生プロセスを明らかにする、新しい道が開かれました。SOX2など、iPS細胞を生み出す転写因子は、転写因子として働く前にまず、ヒストンを含む堅固な複合体に埋もれていた、遺伝子部分のDNAを掘り起こして、新たな遺伝子の発現を準備することが明らかになりました。SOX2などに備わったこの力が、iPS細胞を生み出すだけでなく、発生過程を進める原動力でもあるのです。 | |||
| 第15回 | 中村 壮伸 博士 (産業総合研究所・主任研究員) |
分子動力学法とは何か -物質を記述し、物理法則を考えるための計算手法- | 2026/1/30 14:40–16:10 B107教室 |
| 分子動力学法(MD)は、多数の原子・分子の運動を古典力学に基づいて数値的に追跡し、物質の性質を調べる手法である。本セミナーでは、MDを計算技術として紹介するだけでなく、物理学の中でどのような役割を果たしているのかを整理する。MDは、原子核の運動が電子に比べて遅いという性質に基づき、量子力学を出発点として導かれる近似手法であり、物質科学において広く用いられている。同時にMDは、熱力学的法則を仮定せずに多数の粒子の運動を扱うにもかかわらず、熱力学と整合的な振る舞いを再現することから、統計力学や熱力学の成立を考えるための論証装置としても重要である。本セミナーでは、MDを物質を記述する計算手法と物理法則の成り立ちを考える道具という二つの側面から捉え、その物理学的意義を概観する。最後に論証装置としてのMDの使われかたに関する発表者の研究について簡単に紹介する。 | |||
| 第14回 | 鈴木 健太郎 博士 (東京大学大気海洋研究所・教授) |
雲の粒子と地球の気候 | 2026/1/23 14:40–16:10 B107教室 |
| 空にぽっかりと浮かぶ雲は、太陽の光に対する地球の「白さ」を決めたり、人間が生活する地表に雨を降らせることを通じて、地球の気候において重要な役割を担っています。雲は微小な水や氷の粒子が集まってできたものであり、これらの粒子のミクロな振る舞いが地球温暖化などの気候のマクロな変化に影響しています。このミクロからマクロへの繋がりを理解するために、人工衛星からの地球観測やコンピュータシミュレーションによる研究が進んでいます。この講義では、身近な雲を地球規模でとらえる視点からこれらの研究を紹介します。 | |||
| 第13回 | 安達 俊輔 博士 (東京農工大学大学院農学研究院・教授) |
VisionとTeam -農学研究で1番大切なこと- | 2026/1/16 14:40–16:10 B107教室 |
| 光のエネルギーを有機物のエネルギーに変換する光合成は、地球上における炭素循環の起点となるシステムです。光合成を深く理解し、その効率を高めることが、持続可能な食糧生産を支えるうえで重要となります。光合成は複雑なシステムであるがゆえ、人為的な改変には困難が伴います。オリジナリティの高いアイディアに加え、実現に向けた忍耐力、そしてチーム一丸となった取り組みが必要です。ビジョンの実現に向けて、数多くの方たちと協働してきたこれまでの経験を皆さんと共有いたします。 | |||
| 第12回 | 大井 貴史 博士 (名古屋大学大学院工学研究科・教授) |
分子を創り、振舞いを理解する:触媒作用から生物機能まで | 2025/11/28 14:40–16:10 C102教室 |
| 有機合成化学の魅力は、私達の日常生活に不可欠な有機分子を供給できるだけでなく、新しい分子をデザインして合成し、その働きを理解することで、構造に根差した機能(価値)を生み出せることにあります。その普遍的な意義と可能性を、私達が取り組んできた触媒化学と分野融合型の研究を題材として皆さんと共有できれば幸いです。 | |||
| 第11回 | 谷 篤史 博士 (神戸大学大学院人間発達環境学研究科・教授) |
クラスレート化合物の魅力:反応場や相変化材料から天然ガス資源や氷天体まで | 2025/11/14 14:40–16:10 B107教室 |
| クラスレート化合物(包接化合物)では、ホスト側がカゴ構造をとり、そのカゴにゲスト分子が包接されている。水分子がホスト構造となるものをクラスレートハイドレート(ガスハイドレート)といい、なかでもメタンを包接するメタンハイドレートは日本近海の海底下にも存在する。また、シリカ(SiO2)がホストとなるものをシリカクラスレート(クラスラシル)といい、なかには千葉石や房総石という日本で発見された鉱物も存在する。講演では、反応場や相変化材料など物質としてのクラスレート化合物の魅力や特徴のほか、地球や氷天体に存在するガスハイドレートがどのような役割を持つかを紹介する。 | |||
| 第10回 | 徳永 智春 博士 (名古屋大学大学院工学研究科・准教授) |
電子顕微鏡超概論と応用 ~電子線照射が引き起こす物質の変化~ | 2025/11/4 14:40–16:10 B107教室 |
| 電子顕微鏡は電子線と電磁レンズを用いることで、真空中において物質表面の微細な凹凸情報や、試料内部の原子配列を観察することができる装置である。本講義では、電子顕微鏡を使用することでなぜ高い倍率で試料観察することができるのか?といった電子顕微鏡の基礎から解説するとともに、ガス環境で物質を観察することができる最先端の電子顕微鏡ついても紹介する。 | |||
| 第9回 | 富田 比菜 氏 (高知県林業振興・環境部) |
何者でもない「理系」として生きる | 2025/10/3 14:40–16:10 B107教室 |
| 大学学部生262.8万人のうち、所謂「理系」と称される自然科学系の学生は90.0万人です(2024年度)。これらの理系学生は、学生時代の後半は研究に注力しますが、卒業後に研究者の道へ進むのはごく一部です。現在心身を削って励んでいることが今後活かされるのか、自分は何者になっていくのか、そのような気持ちを抱くこともあるでしょう。今回、今までの人生で得たことが仕事等でどのように活かされているのか、実例を交え、1人の理系としてお話をします。 | |||
| 第8回 | 小西 智也 博士 (阿南工業高等専門学校・教授) |
セラミックス蛍光体の発光効率と材料設計 | 2025/07/18 16:20–17:50 B107教室 |
| 希土類イオンや遷移金属イオンをドープしたセラミックス蛍光体は、照明デバイス、光通信デバイス、偽造防止技術、蛍光バイオイメージングなど、幅広い分野での応用が研究されています。近年、より高い発光効率を目指して、新たな蛍光体の開発も盛んに進められています。本講では、セラミックス蛍光体の発光効率に影響を与える要因について概説し、その上で、高効率化に向けた具体的な材料設計・プロセス設計について、最近の研究動向も交えながらご紹介します。 | |||
| 第7回 | 山下 愛智 博士 (東京都立大学理学部・助教) |
エネルギー課題解決に向けた高温超伝導体及び熱電変換材料の最新研究 | 2025/07/11 14:40–16:10 B106教室 |
| 近年、高温超伝導線材を用いた小型核融合炉の開発が民間主導で活発化しており、核融合炉の実現が現実味を帯びてきている。講演者は、ハイエントロピー合金(HEA)という新しい概念を取り入れた高温超伝導体や熱電材料において、従来材料にない機能性や特性の向上を見出し、実用化に向けた基礎研究等を推進している。HEA概念を取り入れた超伝導体や熱電材料の開発とこれら機能性材料を用いたエネルギー課題解決に向けた最新の動向について講演する。 | |||
| 第6回 | 姫岡 優介 博士 (東京大学生物普遍性研究機構・助教) |
細胞の「死」を数理で理解する | 2025/07/04 14:40–16:10 B107教室 |
| 私たちはいずれ死にます。そうなるとやはり、「死とは何か」を死ぬ前にある程度理解したいと思うのが人情というものでしょう。これまでに、細胞の死に関わる様々な分子が同定されてきています。しかし細胞は数千種類の化学物質が複雑に相互作用し合うシステムなので、少数の分子を詳しく調べるだけでは細胞という「システム」がどのように瓦解して死へと向かうのかを理解することは困難です。我々は数学的なアプローチを用いて、「細胞死」の理論の構築を目指しています。「死んだら生き返ることはできない」という「死」の直感的な特徴を数学的に定式化し、細胞の数理モデルにおける「生」と「死」の境界を定量的に計算することに成功しました。本講義では細胞という複雑なシステムをどのようにしてモデル化し、その破綻である「死」を理解することができるのかについて紹介します。 | |||
| 第5回 | 望月 優子 博士 (理化学研究所仁科加速器科学研究センター雪氷宇宙科学研究室・室長/埼玉大学大学院理工学研究科・連携教授) |
南極の氷からひもとく地球と宇宙とのつながり | 2025/06/25 14:40–16:10 B107教室 |
| 南極大陸の内陸に日本の観測基地「ドームふじ」があります。このドームふじ基地の地下深くの氷を分析すると、地球の過去の気候変動や火山活動に加え、過去の太陽活動も調べることができます。さらには、私たちの天の川銀河系の内部で発生した、重い星の一生の最後の大爆発「超新星爆発」の痕跡を捉えられる可能性もあります。本講義では、これらの研究を紹介し、私たちの住む地球と宇宙とのつながりについて考えます。 | |||
| 第4回 | 今井 一雅 博士 (高知工業高等専門学校・客員教授・名誉教授/KOSEN-1衛星プロジェクトマネージャー) |
超小型衛星KOSEN-1の開発・打ち上げ・運用に携わって | 2025/06/06 14:40–16:10 B106教室 |
| 超小型衛星KOSEN-1は、JAXAイプシロンロケットにより2021年11月9日に打ち上げられ、いくつかのミッションに成功している。KOSEN-1衛星のプロジェクトマネージャーとして、2019年からこの衛星開発に取り組み、打ち上げ後3年半となる運用に携わった経験を元に、超小型衛星開発プロジェクトの面白さについて紹介したい。 | |||
| 第3回 | 高田 礼人 博士 (北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター・教授) |
エボラおよびマールブルグウイルスの研究最前線 | 2025/06/03 16:20–17:50 B107教室 |
| エボラウイルスとマールブルグウイルスはヒトに出血熱という感染症を引き起こします。これらの感染症の発生はアフリカで毎年報告されています。致死率が高くワクチンや治療薬も限定されていることから、これらのウイルスはバイオセーフティーレベル4とよばれる施設で取り扱う必要があります。今回は、私がエボラウイルスの研究を始めた頃から現在に至るまでに行ってきた研究の成果や、対策の確立に向けた今後の課題などについてお話ししたいと思います。 | |||
| 第2回 | 藤田 雅俊 博士 (九州大学大学院薬学研究院・教授) |
がんとは何なのか?:発がんの分子機構、がんの特性、抗がん剤 | 2025/05/23 14:40–16:10 B106教室 |
| がん(悪性新生物)は現在でも最も難治性の疾患の一つであり、日本人の死因の第一位です。しかしこれは、日本人が非常に長寿であることの裏返しでもあるのです。本講義では、「がんとは何なのか?」、「どうしてがんになるのか?」、そして「がん治療」特に「進行がんの治療法について」、分子生物学的視点からそのアウトラインを述べたいと思います。 | |||
| 第1回 | 曲 勇作 博士 (高知工科大学理工学群・講師) |
酸化物半導体の最前線 | 2025/05/16 14:40–16:10 B106教室 |
| 現代の情報化社会は、クラウドコンピューティング、IoT、AIといった技術によって支えられており、それらを実現する基盤として半導体デバイスの重要性はますます高まっています。一方で、情報通信機器による電力消費量も年々増加しており、低消費電力で動作する半導体デバイスの開発が急務となっています。本講義では、半導体技術の歴史を振り返るとともに、次世代の半導体材料として注目されている酸化物半導体について、私たちの研究を交えながら、その最前線をご紹介します。 | |||
| 講演回 | 講演者 | 講演タイトル | 日時/場所 |
|---|---|---|---|
| 第11回 | 櫻井 英博 博士 (大阪大学大学院 工学研究科応用化学専攻 物質機能化学コース・教授) |
スマネンの科学二十余年 | 2024/12/13 14:40–16:10 B106教室 |
| 博士課程在籍中、ひょんなことから出会ったおわん型芳香族化合物「スマネン」について実際に自分で研究を始めたのが1998年ごろ、そして学生と一緒に研究室のテーマとして初めたのが2000年。それからすでに20年以上経過するが、シンプルな構造が故に、まだまだ面白い発見をもたらしてくれる。その魅力の一端でも皆さんに伝えられば幸いです。 | |||
| 第10回 | 横島 聡 博士 (名古屋大学大学院 創薬科学研究科 基盤創薬学専攻・教授) |
環をつくる:多環式天然物の合成研究 | 2024/11/8 14:40–16:50(2つの講演を小休止を挟んで実施) B101教室 |
| 天然物(天然有機化合物)の構造的特徴の一つとして、「複数の環が組み合わさって剛直な骨格を構成している」ことが挙げられる。この特徴は医薬品開発にも有効に働きうるが、「その環構造をいかにして構築するか」は天然物合成の楽しみ(苦しみ)の一つであり、我々の最近の取り組みについて紹介したい。 | |||
| 第9回 | 難波 康祐 博士 (徳島大学大学院 医歯薬学研究部・教授) |
環境問題に貢献する天然物合成 | 2024/11/8 14:40–16:50(2つの講演を小休止を挟んで実施) B101教室 |
| 本講演ではイネ科植物が分泌する天然物「ムギネ酸」を基に開発した砂漠肥料PDMAの開発経緯と実用化への取り組みについて紹介する。また、PDMA実用化のブレイクスルーをもたらした複雑天然物の全合成研究についても併せて紹介する。 | |||
| 第8回 | 石﨑 学 博士 (山形大学 准教授) |
"分散・可溶化"で切り開くエネルギー循環 | 2024/11/8 13:00–14:30 K202教室(講義は録画して期間限定で受講者に限定公開) |
| リーンで持続可能なエネルギー循環システムが求められる。この構築には自然エネルギーを含む豊富な資源からの電力供給や、その蓄電/放電サイクルが不可欠である。また、地政学的リスク回避のための元素戦略が重要である。当研究室では、錯体化学とナノ材料科学を組み合わせ、エネルギー循環技術の確立を目指している。本講演では、材料の"分散・可溶化"をキーワードとした材料・構造エンジニアリングと機能化について説明する。 | |||
| 第7回 | 井戸 啓彰 氏 (株式会社 特殊製鋼所 代表取締役社長) |
「鋼(はがね)」とともに粘り強く -鋳鋼のことや経営のこと- | 2024/10/18 14:40–16:10 B106教室 |
| 「鋳造」は紀元前3000年ほど前のメソポタミア時代から続く、歴史ある製造方法です。時代の変遷とともに作り方をアップデートしながら社会への貢献を続けてきました。そして、現在においても様々な産業に必要不可欠な存在となっています。本講演では「鋳造」の中でも特に強度に優れる「鋳鋼(ちゅうこう)」を取り上げ、その製造方法やモノづくりの楽しさ、難しさ等についてわかりやすく説明します。また、会社経営に関しても少しだけお話ししたいと思います。 | |||
| 第6回 | 稲葉 振一郎 氏 (社会学者・倫理学者、明治学院大学教授) 吉良 貴之 氏 (法哲学者、愛知大学准教授) |
対談:宇宙、人間、長期主義 | 2024/07/30 16:20–17:50 zoom 開催 |
| 人間の倫理的規範を定めるにあたっては、今生きている数に比べて、今後生まれる人類の総数のほうががずっと多いことを考慮に入れるべきではないか。人類(もしくはその後継機種AI)の宇宙進出までを考えると、それは現に流通する善の基準を大きく変えてしまうかもしれない。稲葉振一郎やウィリアム・マカスキルによって唱えられている「長期主義」について深掘りしてみよう、というのが本対談の趣旨である。 | |||
| 第5回 | Dr. Ivan Arraut (Univ. of St. Joseph, Macau) |
Physics in 21st Century: Fundamental aspects and applications | 2024/07/23 16:20–17:50 B105教室 |
| In this introductory talk, we revise the progress of fundamental physics in the last century and its current as well as possible future applications. Currently physics is basically motivated by the unification of the fundamental interactions. Electromagnetism emerged from the unification of electricity and magnetism and it brought by itself the Lorentz symmetry, which was subsequently applied by Einstein to the dynamics of bodies in order to reproduce Special Relativity. Special Relativity is then the unification of Electromagnetism and ordinary dynamics. Subsequently, when gravity was included, General Relativity emerged as the theory of gravity, unifying Special Relativity with gravity. Quantum Mechanics, on the other hand, emerged as the necessity of explaining the UV catastrophe inside the spectrum of black-body radiation discovered by Max Planck. It also helped to explain important phenomena at the microscopic level. It was unified with Special Relativity via Quantum Field Theory where certain physical properties, which could not be explained naturally inside the scenario of Quantum Mechanics emerged from the formalism. The unification then solved several previous paradoxes. Modern physics then based its progress on General Relativity and Quantum Field Theory. Significant advances came when the Electromagnetic interaction was unified with the weak interaction, giving us then the electroweak theory which brought the celebrated Nobel Prize of Weinberg, Salam and Glashow. Subsequently, a theory unifying the electroweak theory with the strong interaction was developed, although it has not yet been fully tested experimentally. Yet still, gravity is the interaction which nobody has been able to unify nor to quantize with the other interactions. In this talk we revise these difficulties. Finally we explain how the tools of fundamental physics, particularly Quantum Mechanics and Quantum Field Theory can help us to solve certain practical problems, including pandemic propagations, Option and Stock market, social collective behavior, etc. |
|||
| 第4回 | 三宅 香帆 博士 (作家・書評家) 筒井 泉 博士 (理論物理学者) |
工科大生はこの本を読め III | 2024/06/11 16:20–17:50 zoom 開催 |
| 定番となった「工科大生はこの本を読め」対談、第三弾です!大学は知識を獲得する場であると同時に、心を自由にし、自分をこれまでの枠から解き放つべき場でもあります。そしていうまでもなく、書物は精神の解放のための主要な武器なのです。文系理系の枠を超えて、二人の本のプロから、本の選び方と読み方の指南をいただきます。 | |||
| 第3回 | 森山 恵 氏 (詩人・翻訳家) |
ウェイリー版『源氏物語』を翻訳して----〈らせん訳〉とはなにか | 2024/05/28 16:20–17:50 zoom 開催 |
| いまからおよそ100年前、イギリス人のアーサー・ウェイリー(東洋学者・ブリティッシュミュージアム学芸員)によって、『源氏物語』は世界ではじめて英語全訳されました。レディ・ムラサキ著『ザ・テイル・オブ・ゲンジ』の誕生です。1925年から33年にかけて全6巻で刊行されたこの英訳『源氏物語』を、わたしは姉の毬矢まりえと現代日本語に再翻訳する、という仕事をいたしました。『源氏物語 A・ウェイリー版』全4巻(左右社、2017年~19年)です。わたしたちは翻訳にあたっていくつかの工夫をしていますが、それを〈らせん訳〉と名付け『レディ・ムラサキのティーパーティ らせん訳「源氏物語」』を著わしました。今回はアーサー・ウェイリーとはどんな人か、拙訳〈らせん訳〉とはなにか、翻訳とはなにか、お話しできたらと思います。 | |||
| 第2回 | 久保 勇貴 博士 (JAXA宇宙科学研究所・研究員 / 作家) |
日本初の土星探査ミッションを作る──超小型外惑星探査計画OPENS── | 2024/05/21 16:20–17:50 zoom 開催 |
| 太陽系において、木星や土星などの巨大ガス型惑星やその周りの氷衛星は、太陽系形成や生命の誕生において重要な役割を果たしたと言われている。他国に次いで日本としてもこの外惑星探査のフロンティアにどう挑んでいくかが問われており、その一つの答えが超小型外惑星探査計画OPENSである。これは、欧米宇宙機関の重厚長大な外惑星探査に対して、高頻度・低コストな超小型探査機で挑むことで、従来のやり方では挑めなかった高リスク/高リターンなミッションに挑戦するというプログラムである。本講演では、プロジェクトの若手工学メンバーである登壇者が、プロジェクトの概要や最先端の研究開発に関して紹介する。質疑応答では、比較的若手の研究者であるという立場も活かし、学生のみなさんと近い立場でお話しできたらと考えている。 | |||
| 第1回 | 近藤 泰弘 博士 (日本語学者・青山学院大学名誉教授) |
文埋め込みモデルによる文学の解析 | 2024/05/14 16:20–17:50 zoom 開催 |
| 近年、単語や文の意味をその分布を使って表現する方法(分散表現・埋め込み表現)が広く用いられるようになりました。特に、大規模言語モデルの発達により、複数の言語に渡る分散表現をベクトルの形で取得できるようになったことは、言語研究に一大変革をもたらしつつあります。本講演では、文埋め込みベクトルを用い、日本文学の中の「文」がどのような形で作品の中で用いられているかを分析します。具体的には、『源氏物語』『古今集』や夏目漱石の作品を対象にして、著者が何を考えて作品を作っているかを示していきます。 | |||
| 講演回 | 講演者 | 講演タイトル | 日時/場所 |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 高橋 舞 博士 (東京大学、ピティナ音楽研究所) |
19世紀から現代までのバッハ演奏史 —コンピュータ・ソフトウェアで分析する演奏スタイルと奏法の変遷— | 2024/01/23 16:20–17:50 未定 |
| クラシック音楽の演奏にも、演奏スタイルの流行があるのでしょうか。 1910年代から現代までのバッハ鍵盤作品の録音を、コンピュータ・ソフトウェアを用いて分析し、 録音のない19世紀については、楽譜の読み方が記載された、当時の演奏のドキュメントである 実用版楽譜を対象に検証します。演奏スタイルの変遷とともに、師から弟子へと奏法が 受け継がれているのか、併せて明らかにします。 | |||
| 第12回 | ジミー・エイムズ 博士 (科学哲学者) アダム・タカハシ博士 (自然哲学史家) |
自然哲学新春対談 --科学と社会と不在の神 | 2024/01/10 10:30–12:00 zoom 開催 |
| 先年度好評だった若手哲学者対談第二弾、今回は科学技術と社会の関係について語っていただきます。「私が世界を経験していると言う事実を、私がその世界の一部であると言う事実とどのように整合させるか」、工学徒にとってものっぴきならぬ、この職業生活上の根本問題への、どのような答えが示唆されるのでしょうか。 | |||
| 第11回 | 中村 正人 博士 (日本大学 教授) |
連分数と天体運動の周期 | 2023/12/19 16:20–17:50 未定 |
| 分数の分母の中にまた分数式があり、そのまた分母に分数式がある...こういったものを連分数といいます。中学のとき√2=1.414...、√3=1.732...など無理やり覚えさせられましたが、連分数を知ると、なんとむなしいことかと思い知らされます。さらに天体の運動の周期や生物に見えるらせん構造などを連分数を用いて理解することができます。一見現実からとおい数学が宇宙の構造の中にどのように現れてくるのか、この講演では不思議な数学と世界の関わりを探っていきます | |||
| 第10回 | 白岩 英樹 博士 (高知県立大学 准教授) |
異端精神の系譜:土佐からアメリカへ | 2023/12/12 16:20–17:50 zoom |
| 「異端精神」と聞くと、斜に構える向きがあるかもしれない。しかし、異端と愚蒙とは同義ではない。従来の枠から我々を解放し、新たな社会の礎となった思想も、元々は異端であった。ここ土佐で生まれた「異端精神」には、いまだ我々が手にしていない「自由」が潜在する。その系譜をたどると、根底にはアメリカの戦争の歴史が眠っていることに気づく。 未知の感染症を経てなお、愚蒙な歴史を繰り返す人類に残された道はどこにあるのか。我々の行く末を共に考え、「異端精神」の可能性を問い直したい。 | |||
| 第9回 | 石田 斉 博士 (関西大学 教授) |
ルテニウム:化学者に愛される元素 | 2023/11/24 14:40–16:10 C102 |
| ルテニウムは、周期表上で鉄の下に位置する元素である。現在ではハードディスクの記録容量を増やすために利用されているが、一般的にはあまり 知られていない。しかし、野依良治博士が、ルテニウム錯体触媒を用いた不斉触媒反応の開発で2001年ノーベル化学賞を受賞するなど、ルテニウム を愛してやまない研究者は多数存在する。どうしてルテニウムは化学者に愛されるのか?ルテニウム錯体のユニークな性質や、それを利用した光増 感太陽電池、光レドックス触媒、人工光合成の研究から、抗がん剤への利用などを紹介し、ルテニウムが化学者から愛される理由を感じてほしい。 | |||
| 第8回 | 中川 真一 博士 (北海道大学 教授) |
非ドメイン型バイオポリマーの逆遺伝学 | 2023/11/21 16:20–17:50 B107 |
| 知らない遺伝子産物があってその機能を知りたいとき、皆さんは何をするでしょう?普通はググりますね。ググって何も出てこないときはどうしたら良いでしょう。多くの研究者は、そこでBLAST検索を行います。一般に、共通の機能を持つタンパク質やRNAは同じような一次配列を持つので、BLAST検索でヒットした保存配列の組み合わせから、新規の遺伝子産物であっても、その機能を大方予測することができるわけです。ところが最近になって、一次配列から機能を予測することができないような遺伝子が実はまだたくさん残されていることが明らかになってきました。本講演では、こういった「へんてこ」な遺伝子の機能を逆遺伝学的なアプローチで明らかにしていく試みについて紹介したいと思います。 | |||
| 第7回 | Prof. Pavel Exner (Czech Technical University) |
Networks that behave differently when you reverse the time direction | 2023/11/14 16:20–17:50 未定 |
| We consider quantum motion on graphs in the situation when the way in which the wave functions match in the nodes is not preserved when we change the direction of time. We focus on the simplest example where the time asymmetry is maximal at a give energy and show that in this situation the high-energy scattering depends crucially on the vertex parity; we will demonstrate implications of this fact for spectral and transport properties in several classes of graphs, both finite and infinite periodic ones. Further- more, we discuss other graphs violating the invariance and identify a class of such couplings which exhibits a nontrivial PT -symmetry despite being self-adjoint. Finally, we show how a square lattice with such a coupling behaves in the presence of a magnetic field when the two time-asymmetry effects compete. | |||
| 第6回 | 倉本さおり 氏 (書評家) 須藤靖 博士 (宇宙物理学者) |
工科大生はこの本を読め(秋) | 2023/10/24 16:20–17:50 zoom |
| 前回好評だった「工科大生はこの本を読め」対談の今年度第二弾です。大学は知識を獲得する場であると同時に、心を自由にし、自分をこれまでの枠から解き放つべき場でもあります。そしていうまでもなく、書物は精神の解放のための主要な武器なのです。文系理系の枠を超えて、二人の本のプロから、本の選び方と読み方の指南をいただきます。 | |||
| 第5回 | 伊東 乾 博士 (作曲家、東京大学教授) +李 珍咏 氏 (東京大学博士課程) |
「生成AIとコネクショニズム」・・・広島から考える新しいものづくりとその倫理 | 2023/10/11 10:30–12:00 zoom |
| 2022年11月、OpenAI社のChatGPT公開以降、「生成系AI」と呼ばれるシステムが急速に社会に普及しつつある。商用では「生成系AI」は「コンテンツ創造」すると喧伝されるが、技術の観点からは自動翻訳と辞書機能の組み合わせに相当する「大規模言語モデルLLM」自然言語処理システムを核に、画像や音響なども合成、程なくAI生成動画などもネットワーク上に氾濫することになるだろう。 そんななか、改めて、人間にこそ可能な「創造」ものづくりとは一体何なのか? 本コースでは「生成AI」などを実現したCNN(畳み込みニューラルネットワーク)が視覚脳生理の実験研究に端を発する経緯(福島邦彦「ネオコグニトロン」大阪1978年)やバックプロパゲーション計算の発明(甘利俊一「確率的勾配降下法」福岡1967年)など私たちの身近で開発された「ちょっとした工夫」が今日のAI化社会のきっかけになった端緒を示すとともに「新しい時代の人間らしいものづくり」とそれが具えるべきモラルについて、1945年8月6日の広島を原点に考えてみたい。遠隔ZOOMの利点を生かし、香川(高松市内:伊東)と東京都目黒区(東京大学駒場キャンパス:李)との3元中継で、典型的なコネクショニズム・デザインのひとつ、迫真型聴覚ARシステムの演示も紹介できたら、と考えている。 |
|||
| 第4回 | Prof. Ivan Arraut (U. of St. Joseph, Macau) |
Fundamental aspects of Quantum Mechanics and Quantum Field Theory | 2023/08/01 16:50–18:20 zoom |
| In this talk, I start explaining the fundamental aspects of Quantum Mechanics and why it seems to challenge common sense. Subsequently, I explain why the first attempts to mix Special Relativity and Quantum Mechanics failed after using a single-particle approach to the problem. I then describe how emerged the idea of Quantum Field Theory, which is a multiparticle version of Quantum Mechanics including successfully the basic principles of Special Relativity. Finally, I explain the importance of the symmetries in Quantum Field Theory, including basic concepts like Spontaneous Symmetry breaking, Higgs mechanism and gauge symmetries. I close the talk by explaining the importance of Quantum Mechanics and Quantum Field Theory in different research areas in physics and I explain how to implement the mathematical principles of these theories in research areas outside physics, like business, finance, economy, individual interactions and others. | |||
| 第3回 | 瀬戸口 信弥 氏 (高知カンパーニュブルワリー 代表社員) |
高知のクラフトビール「TOSACO」~これまでの軌跡とこれからの想い~ | 2023/07/07 15:10–16:40 B104 |
| 移住・起業を志した2016年から現在まで、いわば自分の分身の ように事業に想いこめ、成長させてきました。普段は前しか見てい ないような人間ですが、このような機会に振り返ってみるとその都 度壁を感じながらも、地域や周囲の力を励みに、登り続けるなかで 自分自身をリニューアルしてきました。大学のほど近くに新工場を 構え、創業以来夢見てきた姿の一つは実現しました。事業は新たな 段階に進みましたが、今どんな葛藤を抱えながら、どんな未来を実 現するために動いているのか、赤裸々にお話させていただきます。 学生の皆さんの人生にとって少しでも学びとなる時間になれば幸 いです。 | |||
| 第2回 | 服部 久美子 博士 (数学者) 渡辺 祐真 氏 (書評家) |
工科大生はこの本を読め! | 2023/05/16 16:40–18:20 zoom |
| みなさんは大学にて、単位を揃えるために教科書と格闘している毎日かと思いますが、大学は知識を獲得する場であると同時に、心を自由にし、自分をこれまでの枠から解き放つべき場でもあります。そしていうまでもなく、書物は精神の解放のための主要な武器なのです。文系理系の枠を超えて、二人のプロから、本の選び方と読み方の指南をいただきます。 | |||
| 第1回 | 小西智也 博士 (阿南工業高等専門学校 教授) |
歯科治療に向けた球状微細MTAセメントの合成 | 2023/05/11 15:10–16:10 B104 |
| 1990年代に開発されたMTAセメントはケイ酸三カルシウム(3CaO-SiO2)を主成分とし、歯髄温存治療を可能とする新たな歯科材料として注目されている。MTAセメントの歯管への充填性を向上させるには、球状の粒子で,粒子径が200㎛以下であることが必要である。しかし、粉砕・焼成による従来のセメント製法では焼結により粒径が大きくなってしまうという問題がある。本研究では、ゾルと水溶性塩の混合溶液を出発とする噴霧乾燥または燃焼合成により、粒子同士の焼結を抑制しながら作製する方法を検討した。 | |||
| 講演回 | 講演者 | 講演タイトル | 日時/場所 |
|---|---|---|---|
| 第14回 | 中村正人 博士 (日本大学 教授) |
分子と宇宙 | 2023/01/24 16:50–18:20 zoom |
| 近年宇宙には数多くの種類の分子(星間分子と呼ばれる)が存在することがわかってきました。我々が直接行くことができない遠い宇宙のかなたになぜそんな分子があると分かるのでしょうか?簡単な分子がほとんどですが、たとえばサッカーボールの形をした分子やハチの巣構造を持つ分子が存在することがわかってきました。なぜそのような分子ができたかはまだ謎に包まれています。かつて天文学と化学は大変遠い分野と思われてきましたが、いまは親戚同士になっています。 | |||
| 第12, 13回 | ジミー・エイムズ 博士 (舞鶴工業高等専門学校 助教) アダム・タカハシ博士 (東洋大学 助教) |
サイエンスはどこから来たか:中世スコラ哲学、そして古代自然哲学 | 2022/12/20 16:50–20:00 zoom |
| 数ある高文明地域のうちで、なぜ欧州からのみ自然科学が生まれてきたのか。この重要極まりない問いをめぐって、科学史、科学哲学の若手俊英2名に立論をいただき、それをめぐって聴衆も参加しての議論を進めたいと思います。モデレーター全卓樹。 参考文献: アレクサンドル コイレ著、 横山雅彦訳「閉じた世界から無限宇宙へ」(みすず書房 1973) アダム・タカハシ 著「哲学者たちの天球―スコラ自然哲学の形成と展開」(名古屋大学出版会 2022) |
|||
| 第11回 | 須藤 靖 博士 (東京大学 教授) |
世界はゆらぎできている? ボルツマン脳とボルツマン宇宙 | 2022/12/13 16:50–18:20 zoom |
| 我々が見ることのできるこの世界の多様性と豊穣さは、つまるところ完全な一様性からずれた微小なゆらぎから生まれたものだといえます。例えば、宇宙に存在する天体諸階層は、宇宙誕生時の量子ゆらぎが古典的な密度ゆらぎになり、膨張宇宙における重力的成長を経た結果です。その中で生まれた生命がダーウィン的進化を経て知性が誕生したわけですから、世界の森羅万象はゆらぎから生まれたことになります。 一方、未来の宇宙において気が遠くなるほどの時間だけ待てば、このようなダーウィン的進化ではなく、単なるゆらぎから突如として、知性を備えた巨視的な構造が生まれる可能性はゼロではありません。いかに確率が低かろうとゼロでない(つまり、物理法則に矛盾しない)限り、将来そのような「ボルツマン脳」が誕生する可能性があるどころか、実はすでにどこかでそのような構造が誕生しているかもしれません。 はたして全先生が「ボルツマン人間」である可能性はどこまで否定できるのでしょうか。今回は、そのような限りなく怪しい一方で、科学的に否定することが難しい疑問を考察しつつ一緒に悩んでみたいと思います。 |
|||
| 第10回 | ジョゼフィーヌ・ガリポン 博士 (慶應義塾大学 先端生命科学研究所 特任講師) |
生合成メカニズムを解明するためのポータブルでスケーラブルなシステムに向けて | 2022/11/29 16:50–18:20 zoom |
| 細胞は、環境からの刺激に適応しながらも自己制御・組織化・複製可能なマイクロファクトリーと言える。また、ナノからマクロまでの各スケールにおいて構造を形成する機能を有する。本講義では、分子生物学に限らず、材料科学・工学分野をも含む異分野融合により、生物構造の機能解析と複雑な環境適応メカニズムの解明を通し、高精度・持続可能なバイオファブリケーションの新たな活用法を創出するバイオ工学の研究開発を紹介する。 | |||
| 第9回 | 石谷 治 博士 (東京工業大学 理学院 化学系 教授、広島大学 先進理工系科学研究科 特任教授(兼任)) |
人工光合成 ー太陽光エネルギーを用いて二酸化炭素資源化を目指すー | 2022/11/25 13:30–15:00/K-HALL + オンデマンド |
| 地球の温暖化と化石資源の枯渇は人類にとって甚だ危険な問題である。これらは何れも、人類が化学原料およびエネルギー源として多量の化石資源を長年利用し、最終的にそのほとんどを燃焼することで多量のCO2を大気中に放出し続けていることにより生じてしまう。光合成のように、太陽光をエネルギー源としてCO2を還元し、有用でエネルギーを蓄えた有機化合物を合成する技術(人工光合成)を我々が持つことができれば、これらの問題を一挙に解決できる可能性がある。本講義では、CO2の資源化を目指した人工光合成に関する研究を紹介する。 | |||
| 第8回 | 西山敦哉 博士 (東京大学医科学研究所准教授) |
エピジェネティックな情報はどのように複製されるのか? | 2022/10/14 15:30–18:00(2つの講演を小休止を挟んで実施) C101教室 + オンデマンド |
| 染色体は遺伝情報の本体であるDNA、そしてその発現を制御するDNAメチル化やヒストン修飾をはじめとしたエピゲノムの二種類の情報を持つ。細胞特異的な遺伝子発現を維持するためには、染色体の複製時に、この二つの異なる情報を正確に娘DNAに継承することが重要である。DNA複製の分子機構は現在詳細に理解されているのに対し、エピゲノムの複製機構には未だ不明な点が多い。本談話会では、DNAメチル化継承の仕組みを中心に、エピゲノム複製の分子機構について議論する | |||
| 第7回 | 高橋達郎 博士 (九州大学理学部教授) |
遺伝情報を正確に維持、継承するしくみ | 2022/10/14 15:30–18:00(2つの講演を小休止を挟んで実施) C101教室 + オンデマンド |
| 生物の遺伝情報はDNAの核酸塩基の並びに記録される。遺伝情報の維持や継承反応は、ワトソン・クリック塩基対と呼ばれる核酸塩基の相補的な対合をもとに動作する。ところが、ワトソン・クリック塩基対は様々な原因で破綻することがある。本講演では、細胞がワトソン・クリック塩基対の破綻をどのように検知し、遺伝情報の維持、継承の正確性をどのように守るかについて紹介したい。 | |||
| 第6回 | 北村 紗衣 博士 (英文学者、武蔵大学 准教授) |
批評はどのようにすればよいのか?~フェミニスト批評を実践する | 2022/07/12 16:50–18:20 zoom |
| 批評は小説や映画、絵画といった芸術作品のみならず、スポーツや広告、ゲームまで、あらゆるテクストに対して行うことができるものである。批評はテクストをめぐって行われるコミュニケーションの一種であり、コミュニティを作る機能を持っている。この講演ではこうした批評の機能をふまえた上で、ジェンダーに着目したフェミニスト批評を実際にやってみることで批評に対する理解を深めることを目指す。 | |||
| 第5回 | 西森 拓 博士 (明治大学 研究 先端数理科学インスティテュート 教授) |
必ずしも賢くない個たちによる賢い組織づくり ―アリの社会行動を行動計測と数理モデルから解明する― |
2022/06/28 16:50–18:20 zoom |
| アリはハチと共通の祖先から進化し、現在地球上のほとんどの地域で繁栄を謳歌しています。 私たちの研究室ではアリのコロニー(巣を共有する集団)が特定のリーダー無しで複雑な協調行動---分業制や時間交代制---を行って生産性を上げていることに着目し、その基本メカニズムを探るために、実験および数学モデルなどを組み合わせて研究を行ってきました。一例として、コロニー内の全てのアリにRFIDチップを貼り付け(図参照)、個体識別しながら集団としての役割分担の移り変わりを長時間にわたって自動計測しています。そこから分かってきたのは、従来広く信じられてきたコロニー内での分業発生機構の仮説(=各タスクに関する休憩状態から労働状態への遷移確率がアリ毎の内在的性質として保有されている)が正しくないかも知れないということです。講演では、様々なアリの興味深い行動や分業制について紹介した後、最新の実験データをもとに従来の分業発生の仮説を否定的な方向から検証し、採餌に関する「役割分担表」は時間に応じて大きく変化することを示していきます。
参考文献 [1] O. Yamanaka, M. Shiraishi, A. Awazu, H. Nishimori: Verification of mathematical models of response threshold through statistical characterisation of the foraging activity in ant societies’, Scientific Reports 9 (1), 8845 (2019). [2] 山中治,白石允梓,西森拓: 社会性昆虫の固定反応閾値モデルの大規模データによる検証, 計測と制御, 59 巻 2 号 p. 104-110(2020). |
|||
| 第4回 | 須藤 靖 博士 (宇宙物理学者、東京大学教授) |
見えないはずのブラックホールを見る | 2022/06/21 16:50–18:20 zoom |
| 2015 年に大質量連星ブラックホールからの重力波が検出された。この発見をリードした米国の3人の物理学者は「LIGO検出器および重力波の観測への決定的な貢献」に対して、2017年のノーベル物理学賞を受賞した。さらに2020年のノーベル物理学賞は、一般相対論が必然的にブラックホール形成を導くことを示した理論家のロジャー・ペンローズと、銀河系中心に超巨大ブラックホールが存在することを明らかにした観測天文学者2名に与えられた。また、2022年5月12日、国際共同プロジェクトEvent Horizon Telescope(事象の地平線望遠鏡)は、その銀河系中心ブラックホールのシャドー撮像結果を世界で同時発表したことも記憶に新しい。このように見えないはずのブラックホールは、今や天文学における重要な観測対象として確立している。今回は、ブラックホールをめぐる最近の天文学について紹介する。 | |||
| 第3回 | 田崎 晴明 博士 (理論物理学者、学習院大学教授) |
相転移と臨界現象の統計物理学:小さくてあまり面白くないものがすごくたくさん集まると勝手にびっくりするような面白いことをやり始めるという話 | 2022/06/07 16:50–18:20 zoom |
| 初等的に解析できる相転移現象のモデルであるパーコレーションを出発点にして「ミクロとマクロを結ぶ科学」である統計物理学の一端を紹介する。 | |||
| 第2回 | 三宅 陽一郎 博士 (人工知能学者、株式会社スクウェア・エニックス) |
デジタルゲームにおける人工知能 | 2022/05/17 16:50–18:20 zoom |
| 現代におけるデジタルゲームで応用されている人工知能技術とその歴史についてお話いたします。記号主義型AIから、コネクショニズム的AI、およびその融合まで、幅広く解説いたします。 | |||
| 第1回 | 崎山 直樹 博士 (アイルランド近現代史研究者、千葉大准教授) |
北アイルランドとBrexit ‒矛盾と暴力‒ | 2022/04/26 16:50–18:20 zoom |
| 2013年から始まるイギリスのEU離脱の動きは社会の更なる分断をもたらした。特にこの分断は、イギリス社会において社会的な繋がりが最も弱い地域である北アイルランドにおいて大きな歪みをもたらしている。本講演では、19世紀以降のアイルランド・ナショナリズムの流れを概観した上で、1960年代からの北アイルランド問題そして現代のBrexitによって生じている社会変容を考察する | |||
| 講演回 | 講演者 | 講演タイトル | 日時/場所 |
|---|---|---|---|
| 第14回 | 呉座 勇一 博士 (歴史学者) |
戦国大名の外交に学ぶ | 2022/02/01 16:50–18:20 zoom |
| 【概要】応仁の乱以降、日本は戦国時代に突入しました。戦国時代というと、合戦やだまし討ちばかりしていたイメージがありますが、 同盟や講和によって戦争を回避する努力も多く試みられており、現代人にとっても示唆に富んでおります。 冒頭、応仁の乱に簡単に触れつつ、戦国大名の巧みな外交戦略について語ります。 | |||
| 第13回 | 川添 愛 博士 (言語学者) |
無意識の言語知識を眺めよう ——理論言語学の観点から—— | 2022/01/18 16:50–18:20 zoom |
| 【概要】私たち人間は言葉を理解するとき、膨大な知識を無意識に働かせている。たとえば、「『佐藤氏を課長として採用する』と『代官山を拠点として活動する』は、文法的にどう違う?」と訊かれてとっさに答えられる人は多くないだろうが、それでも無意識のレベルではこれらの構造の違いを認識している。理論言語学は、こういった「無意識の言語知識」を対象とする研究分野であり、その成果の中には、言葉の自然さ・不自然さ、曖昧さなどについての知見が多く含まれている。本講演では、それらの知見の中から、より多くの人にとって有用と思われるものをいくつか紹介する。 | |||
| 第12回 | 秋田 麻早子 氏 (美術史学者) |
絵画の構造を読み解く | 2022/01/11 16:50–18:20 zoom |
| 【概要】絵画を見るとき「何が描かれているのか」「描かれた背景はどういうものか」といった主題やコンテクストが話題になりがちです。しかし、その絵が「どう描かれているか」という形式を観察することも同じくらい大切です。そもそも絵画はなぜ四角いのか。四角い画面ゆえの制約とは何か。丸い絵画と比較しながら、四角い絵画の構造とその効果を読み解いていきます。 | |||
| 第11回 | 粟屋 祐 博士 (ロチェスター大学・助教授) |
共有知識の悲劇 | 2021/12/14 16:50–18:20 zoom |
| 【概要】奴隷達はどのようなとき力を合わせ王を倒せるか?そのためには個々に王は実は弱いと知っているだけでは不十分で、他の奴隷達も王が弱いと知っている、という事を知っている、という事を知っている、というのが「無限に」続かなければならない(これを共有知識という)。では、奴隷たちはどのような時に「王が実は弱い」という情報を共有知識に出来るか?奴隷全員で一堂に会しそこで「王が実は弱い」という証拠を見ればよい。それが不可能で一度に合う人数を限らなければならない時はどうすればよいか?一度に合う人数が多ければ多いほど共有知識に近づけるか?というと実はそうではない。一度に合う人数が多すぎるとかえって反乱は起きにくくなる。というお話です。 | |||
| 第10回 | 須藤 靖 博士 (東京大学・教授) |
マルチバース的世界観 | 2021/12/07 16:50–18:20 zoom |
| 【概要】自然科学においては、仮にどれほど優れた理論体系であろうと実験結果と矛盾すれば直ちに「間違った理論」として却下されます。これが数学と自然科学との本質的な違いであると学んだことがあるかもしれません。しかしよく考えると、それは理論が間違っているのではなく、我々が住むこの宇宙(ユニバース)がそれを採用していないだけかもしれません。言い換えれば、間違っているのは理論ではなく、この宇宙なのではないでしょうか? この宇宙の森羅万象は標準素粒子モデルと標準宇宙論モデルによって見事に説明されますが、そのモデルには数多くの不自然さが残っています。そしてそれは、この宇宙だけに特有なものかもしれません。いっそのこと宇宙は唯一無二ではなく、無数に存在するとするマルチバースという考えを認めれば、それらの不自然さが解消される可能性があります。しかしながらその考え方は検証可能ではないため、通常の意味での科学的仮説とは言えません。我々が住むユニバースのどこが不自然なのか、マルチバースとは一体何なのか。物理学と哲学の境界に位置するマルチバース的世界観を紹介します。 | |||
| 第9回 | Jimmy Aames 博士 (舞鶴工業高等専門学校・助教) |
相対論的宇宙における時間の流れ:因果ダイアモンドとゲーデルの時間論 | 2021/11/30 16:50–18:20 zoom |
| 【概要】「時間の流れ」ほど私たちにとって当たり前のものはない。しかし、時間が流れるというこの当たり前の常識が、現代物理学、とりわけ相対性理論と相性が悪いということが盛んに指摘されている。本講演では、いかにして相対論と整合する形で時間の流れを定式化できるか、という問いを探究したい。こうした試みの中で特に有望だと思われるのが、哲学者のSteven SavittとRichard Arthurが提唱する「因果ダイアモンド」理論である。本講演ではこの因果ダイアモンド理論とその利点を紹介する。さらに、物理学をベースに時間の流れを考えるにあたって避けて通れないのが、論理学者・数学者Kurt Gödelによる有名な「時間の非実在性」の論証である。Gödelは、一般相対論の基本方程式であるEinstein方程式の解として、いわゆる「回転宇宙」モデルを発見した。これは、ある意味において過去へのタイムトラベルを許すという奇妙な性質を持つ宇宙である。Gödelはこの新しい宇宙モデルを根拠に、私たちが経験する時間の流れは一種の幻想であると論じたが、本講演では、Savitt-ArthurのアプローチによってGödelの議論に応答できることを示したい。 | |||
| 第8回 | 富谷 昭夫 博士 (大阪国際工科専門職大学・助教) |
機械学習と物理学 | 2021/11/9 16:50–18:20 zoom |
| 【概要】本講演では、機械学習と物理学について近年の話題を含め基本的な所から説明する。機械学習はすでに社会応用されている技術であり、データから構造を読み取り、明示的なプログラミングなしにプログラムの動作を設定するものである。また物理学は身の回りの物質の構成や物質間の力を調べる学問である。一見すると関係が内容に思えるが、根幹に共通する発想がある。本講演ではそれらも含め、議論していく。 | |||
| 第7回 | 木村 元 博士 (芝浦工業大学 教授) |
ミクロな世界の不思議と情報科学への応用 --- ベルの定理とエンタングルメントと量子情報科学 | 2021/07/13 16:50–18:20 zoom |
| 【概要】原子や素粒子などが活躍するミクロな世界は量子力学によって極めて高い精度で説明されるが,その全貌を理解しているものは未だ誰もいない.とりわけ量子力学は,私たちの持つ常識的な考えの1つである実在感・存在感を根底から覆してしまった.例えば,今「月」を見ていなくても,「月」は(いつもの場所に)あると考えるのは自然な考え(実在)であるが,ミクロな世界になると,この常識が通用しなくなることがわかる.正確に言うと,このような実在を持ち出すと,それは空間を超えて影響が伝わる奇妙な非局所性が付きまとうことが知られている.これをベルの定理という.非局所性は,局所的な存在である人類にとって極めて大切な仮定であるため,ミクロな世界では実在的な考えを放棄せざるを得ないことになる.哲学のような議論に感じるかもしれないが,これは現代物理学で真っ向から考えなければならない事実なのである.これに対し,ここ20-30年の間,この不思議な性質(エンタングルメントと呼ばれる)が情報科学へ応用できることがわかってきた.量子コンピュータ,量子暗号,量子テレポーテーションなどを扱う量子情報科学である.本講義では,ベルの定理を中心に解説し,時間が許せば量子情報科学への応用まで話したい. | |||
| 第6回 | 伏信 進矢 博士 (東京大学 教授) |
酵素の化学と共進化(第二部) | 2021/06/29 16:50–18:20 zoom |
| 【概要】酵素は生物が作り出す触媒で、様々な化学反応の進行を助けます。この講義では、酵素が引き起こすユニークな化学反応と、ヒトと腸内細菌の間で起こった「共進化」について、酵素(タンパク質)の立体構造を中心にご紹介します。1つ目の話題は、タマネギを切った時に涙をもよおす化学物質を産生する「催涙因子合成酵素」について。もう1つは、ヒトが供給する糖鎖(母乳のオリゴ糖など)を分解するように分子進化してきたと考えられる、ビフィズス菌の酵素についてです。 | |||
| 第5回 | 梅田 道生 博士 (駒澤大学 准教授) |
日本の選挙制度とさまざまな主体の戦略的行動 | 2021/06/22 16:50–18:20 zoom |
| 【概要】報告者はこれまで日本の選挙制度の下でのさまざまな主体の戦略的行動について研究してきた。政治学では従来選挙制度に基づく各種の「法則」,例えば小選挙区制を採る国では二大政党制が生じる,等の議論が行われている。日本は衆議院と参議院では多数代表型と比例代表型を組み合わせた混合選挙制度,他方地方議会では大選挙区制度,と複雑かつ国際的にも珍しい選挙制度を組み合わせて用いている。本報告ではこうした制度のもとで政党や候補者,有権者などの主体がどのように戦略的に行動しているのか,またこれが日本における民主政の在り方にどのような影響を及ぼしているのかについて論じたい。 | |||
| 第4回 | 宮川 剛 博士 (藤田医科大学・総合医科学研究所 教授) |
脳内中間表現型~遺伝子と行動をつなぐためのキーコンセプト~ | 2021/06/15 16:50– zoom |
| 【概要】演者らは知覚・運動機能や高次認知機能のテストを含む「網羅的行動テストバッテリー」を用いて多くの系統の遺伝子改変マウスの心理学的特性を評価してきた。この中で、顕著な異常プロファイルを示す系統を複数同定しているが、これらのマウスの脳を各種の手法で調べたところ、脳の一部の細胞が疑似的未成熟状態に留まっている現象が共通して生じていることを発見した。本講演では、精神・神経疾患の研究との関連にも触れつつ、遺伝子、脳、行動の関係を理解していくための戦略についての議論も行う。 | |||
| 第3回 | 梶谷 懐 博士 (神戸大学 教授) |
「幸福な監視国家」の経済学―産業政策・監視・文化- | 2021/06/08 16:50–18:20 zoom |
| 【概要】報告者は、高口康太との共著の中で、ビッグデータを用いて市民に利便性と経済的利益を与える一方でその情報を使って社会の安定や治安の向上を図ろうとする中国の統治体制を、パターナリズムと功利主義とが結びついた「幸福な監視国家」であると評価した。その状況は2020年のコロナ禍中国政府・社会のコロナ対策の取り組みにおいて一層明確になった。本講義では、「幸福な監視国家」中国の台頭が、現在の米国を中心としたリベラルな国際経済秩序に与える影響について、産業政策・監視技術・文化的差異という三つの視点から論じたい。 | |||
| 第2回 | 伏信 進矢 博士 (東京大学 教授) |
酵素の化学と共進化(第一部) | 2021/05/25 16:50–18:20 zoom |
| 【概要】酵素は生物が作り出す触媒で、様々な化学反応の進行を助けます。この講義では、酵素が引き起こすユニークな化学反応と、ヒトと腸内細菌の間で起こった「共進化」について、酵素(タンパク質)の立体構造を中心にご紹介します。1つ目の話題は、タマネギを切った時に涙をもよおす化学物質を産生する「催涙因子合成酵素」について。もう1つは、ヒトが供給する糖鎖(母乳のオリゴ糖など)を分解するように分子進化してきたと考えられる、ビフィズス菌の酵素についてです。 | |||
| 第1回 | 伊東 乾 博士、李 珍咏 氏 (東京大学 准教授、博士課程) |
プリンテッド・エレクトロニクスとしなやかなコンピュータ(このリンクで開く「参加クイズ」を各自考えてきてください) | 2021/05/24 16:50–18:20 zoom |
| 参加クイズ:もし現在<硬い>コンピュータや機械が柔らかかったり、変形可能になったら、どんな未来が開かれるか、考えてみてください:(当日教室で無作為にお訊ねします。ZOOMを用いる対話型のゼミナール・セッション形式で準備しています | |||
| 講演回 | 講演者 | 講演タイトル | 日時/場所 |
|---|---|---|---|
| 第9回 | 小林 未知数 博士 (京都大学助教) |
科学における秩序とトポロジー | 2020/02/04 10:30–12:00 K-HALL |
| 【概要】自然界には様々なスケールにおいて秩序構造が出現する。最もミクロなスケールで親しみなれたものが水から氷への転移であろう。氷は水と違って水分子が規則正しく配列した状態である。水から氷の転移のような、秩序構造の発現メカニズムを正確に理解することは科学における難問の1つであると言っても過言ではない。一方、トポロジーとは図形を研究する学問であるが、大きさや形といった情報を排除し、注目する図形の最も本質的な情報(例えば穴がいくつ開いているか)のみを議論する学問である。 自然界における秩序構造の発現に関して、トポロジーの概念を用いた理解が上手く適用できる場合が少なくない。講演ではいかにトポロジーのアイデアが自然界の秩序構造を理解するのに役立っているのかを紹介する。 |
|||
| 第8回 | 大場 みち子 博士 (公立はこだて未来大学教授) |
ライティングとプログラミングから思考過程を探る | 2020/01/28 10:30–12:00 B107 |
| 【概要】次期学習指導要領では思考力の育成が重要視されている。 「考える力」を育てるには、考えた結果にもとづいて後から指導するより、考え方をその場で指導できる方が効果的である。どのように考えて答えを導こうとしているかという思考過程が分かれば、誤りの分岐点や思考のループ、いきづまりなどをとらえて適切に指導できるであろう。講演者はこれまでライティングやプログラミングに着目して思考過程を編集操作から探る研究を進めてきた。ライティングの編集操作を記録するアプリケーションや文章やプログラムをパズル化してその並べ替え操作を記録するアプリケーションを開発して思考過程を解明している。これらの研究アプローチとこれまでの成果を紹介する。 | |||
| 第7回 | 須藤 靖 博士 (東京大学教授) |
宇宙と惑星の観測から生まれた新たな世界観 | 2020/01/24 10:30–12:00 B107 |
| 【概要】2019年のノーベル物理学賞が、米国プリンストン大のジェームズ・ピーブルズ教授、スイス・ジュネーブ大のミシェル・マイヨール教授と同大(英国ケンブリッジ大学兼任)のディディエ・ケロー教授の3名に授与されることになった。ピーブルズ教授は現代宇宙論の基礎理論を確立し、マイヨール教授とケロー教授は太陽以外の恒星の周りの惑星の発見を通じて系外惑星研究という新たな分野を開拓した。宇宙と惑星という全く異なるスケール天体現象の観測から明らかとなった最新の世界観を紹介する。 | |||
| 第6回 | 吉良 貴之 氏 (宇都宮共和大学専任講師) |
理工学の法哲学(2):「ルール」を国ごとに比較しよう | 2020/01/17 10:30–12:00 B107 |
| 【概要】科学技術の開発にあたっては社会的なルールが必要です。前回に引き続き、アメリカ、EU諸国、日本、中国などでの「ルール」の国際比較を考えます。「ルールメイキング」そのもので既に競争がなされている、という状況を見ていきます。 | |||
| 第5回 | 吉良 貴之 氏 (宇都宮共和大学専任講師) |
理工学の法哲学(1):「ルール」を多様な視点から考えよう | 2020/01/14 10:30–12:00 B107 |
| 【概要】科学技術の開発にあたっては社会的なルールが必要です。そのルールは、不確実なものをただ規制するだけでなく、イノヴェーションをうまく促進するものでもあるべきでしょう。ここでは「法」のあり方を中心に、その役割分担(司法、行政、立法……)を踏まえ、規制と促進のベストミックスを考えていきます。最先端の科学技術の様々な例を素材に、できるだけ根本的な問いを考えていきます。たとえば「AI裁判官」は望ましいといえるでしょうか。 | |||
| 第4回 | 富谷 昭夫 博士 (理研/BNL 基礎科学特別研究員) |
ディープラーニングと科学 | 2019/12/13 10:30–12:00 B107 |
| 【概要】AI技術は未来の技術ではなく、現在すでに応用されている使える技術である。なかでもニューラルネットワークを用いたディープラーニング(深層学習)はGoogle 翻訳などに用いられている。深層学習が有用であるのは、大量のデータからその規則性を見出して、結果を導く事ができるため複雑なデータなどを処理することが出来るからである。一方で物理学において波動関数や場の配位など大きなデータを処理する場面があるため応用可能である。本講演ではディープラーニングを始めとした機械学習の手法が物理にどう応用されているかを解説する。 | |||
| 第3回 | 船越 賢一 博士 ((一財)総合科学研究機構 中性子科学センター 研究開発部次長) 杉山 純 博士 (同 サイエンス・コーディネーター) |
量子ビームを用いた材料解析 | 2019/11/14 10:30–12:00 C102 |
| 【概要】茨城県東海村には、世界最高強度の陽子加速器施設 J-PARC があります。ここでは、ほぼ光速まで加速した陽子を種々の標的にぶつけて、多彩な二次粒子を生成しています。特に物質生命科学研究施設で生成する中性子とミュオン(所謂、量子ビーム)は、多くの物質研究に利用されています。今回は、どのように中性子とミュオンを生成し、それらを使ってどのような研究がなされ、どのような成果が出ているかを簡単に説明します。J-PARC の建設と運営には膨大な国費が使われています。また学術的な研究に対して、利用者の制限はありません。皆様にも是非とも使っていただきたいと思います。 | |||
| 第2回 | 川沢今村 百可 博士 (ペンシルバニア州立大学准教授) |
ゲノム科学と医療への応用 | 2019/06/20 14:40–16:10 C102 |
| 【概要】ゲノム(Genome)とは、Gene(遺伝子)がたくさん集まった(Ome)ものを指す、なんとも曖昧模糊とした用語です。遺伝子は親から子へ伝わる形質(肌の色だったり、血液型だったり)で、これに異常が起こると遺伝病やガンなどの病気になります。 ゲノムはDNAという化学物質でできており、これが1000個とか10000個とかつながると一遺伝子ができます。ゲノム科学とは、DNA配列(遺伝情報)を調べることで、医学の進歩や、生命の謎を解き明かす学問です。平成の時代、ゲノム科学は飛躍的な進歩を遂げました。アマゾンで2万円も出せばあなたのDNAプロファイリングが可能だし、次世代シーケンサーを使えば何十億もあるDNA配列を一晩で読み解くことができ、遺伝子検査の応用の幅を一気に広げました。ごく微量のがん細胞からDNAの変異を読みとり、その変異を修正する薬を投与する「がんのゲノム医療」は、従来の抗がん剤治療では救えなかった患者さんの大きな希望の光です。医学、生物学、化学、エンジニアリング、コンピューターサイエンス、統計学、様々な知識と技術が集約して初めて可能となるゲノム医療。あなたもゲノム科学を学び、実生活への応用に活かしてみませんか?そして、家族の誰かががんになった時、その知識を活かし、共に闘いませんか? |
|||
| 第1回 | 谷畑 勇夫 博士 (北京航空航天大学教授) |
原子核の新しい構造と宇宙における原子核の役割 | 2019/05/14 14:40–16:10 講堂 |
| 【概要】原子核は原子とは違って、大きな中心がなく民主的な構造を持っている。我々を形作っている元素は宇宙における一連の原子核の合成によって作られてきた。宇宙の歴史の中で、何時、どこで、どの様にして、元素が作られてきたかを原子核の構造の知識と関連づけて考察する。内容を列挙すると(1)陽子と中性子から作られている原子核の構造について最も基本的な、大きさやマジックナンバーについて学ぶ。(2)宇宙の進化に関連した原子核の性質、ベータ崩壊や核反応などの基礎を学ぶ。(3)それらの知識をつなぎ合わせることによって誕生から現在に到るまでの宇宙の進化の中で原子核がどんな働きをしてきたのかを元素合成という視点から学ぶ。 | |||
| 講演回 | 講演者 | 講演タイトル | 日時/場所 |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 鈴木 紀之 博士 (高知大学准教授) |
自然淘汰の本質を考える:「求愛のエラー」の事例から | 2019/01/29 10:30– K-HALL |
| 【概要】自然淘汰による進化によって生物の行動や形は最適化されます。身の回りの動物や植物を観察すれば、生存や繁殖のために進化したすぐれた仕組みを見て取れるでしょう。しかし自然界には、一見すると不合理な、最適化されていないような形質も少なくありません。そうした無駄ともいえる進化がなぜ生じたのか、その結果として生物の集団の動態や多様性の維持にどのような影響が出るのか、これまでほとんど分かっていませんでした。本講演では、昆虫のオスが他種のメスと交尾しようとする「求愛のエラー」を題材に、不合理な行動が進化してしまう理由と、ニッチや分布といった生物群集のパターンに波及していくメカニズムについて解説します。 | |||
| 第12回 | 神谷 之康 博士 (京都大学教授) |
ブレイン・デコーディング:脳から心を読む技術 | 2019/01/22 10:30– K-HALL |
| 【概要】「脳から心を読む機械」は古くからフィクションに登場しますが、その可能性が科学的議論の対象となったのは、ごく最近のことです。脳の信号は行動や心の状態を符号化している「コード」と見なすことができます。そして、そのコードを「デコード」することが脳から心を読むことにつながります。私の研究室では,コンピュータサイエンスで開発されている機械学習や人工知能の技術を応用して、身体や心の状態に関するさまざまな情報を脳信号パターンからデコードする方法の開発を進めています。本講演では、人が見ているものやイメージしたものを脳から解読する方法を中心に紹介しながら、コミュニケーションや表現の手段としてのブレイン・デコーディングの可能性について議論します。 | |||
| 第11回 | 野中 弘二 博士 (埼玉県防災学習センター総務渉外グループ長) |
失敗学の事例検証 -研究計画や安全設計を事例として- | 2019/01/15 10:30– K-HALL |
| 【概要】大学では様々なユニークなアイデアや社会の要請から研究計画や設計が日々進められています。しかし、そのどれもがうまくいき日の目を見る訳ではありません。また過去の経験に基づく安全設計も、現場では想定外の事態で機能しない事例が続きます。 かつて企業や大学の工学研究者として、またその後の筆者の経験した失敗事例と原因を紹介・検証し、皆さんの事例を聴きながら失敗の種がどこに潜んでいるかを議論します。 |
|||
| 第10回 | 吉良 貴之 氏 (宇都宮共和大学専任講師) |
科学技術の法哲学:「法」が得意なこと、そうでないこと | 2018/12/21 10:30– K-HALL |
| 【概要】科学技術の研究開発にあたっては社会的なルールが必要です。そのルールは、不確実なものをただ規制するだけでなく、イノヴェーションをうまく促進するものでもあるべきでしょう。今回は「法」のあり方を中心に、その役割分担(司法、行政、立法……)を踏まえ、規制と促進のベストミックスを考えていきます。もしかしたら「法」そのものがいらなくなる、そんな未来を想像してみるのもいいかもしれません。 | |||
| 第9回 | 別府 俊幸 博士 (松江工業高等専門学校教授) |
エンジニアリング・デザイン:製品デザインを通じた社会への貢献 | 2018/12/18 10:30– K-HALL |
| 【概要】みなさんの周りを見てください。たくさんの「製品」があります。これらの「製品」はすべて、人々の要求を解決するために誰かがデザインしたものです。大学で学ぶ知識や技術は、それらを活用して「デザイン」を生み出してこそ、人や社会や環境に役立ちます。役立つためには、何が必要でしょうか?--よい製品とはどういうものか、よりよいデザインを作るためには何を、どう考えれば良いのかを議論します。 | |||
| 第8回 | 井上 光輝 博士 (豊橋技術科学大学教授) |
人工磁気格子における磁気的位相干渉と光・高周波応用 ※IEEE Magnetics Society Distinguished Lecture for 2018 |
2018/11/30 13:00–14:30 K-HALL |
| 【概要】人為的な構造を導入した人工磁気格子(AML)で生まれる磁気的磁気干渉を利用して、これを磁気と結合した波動操作に用いる手法と、この手法を用いた光・高周波応用について述べる。AMLは、光波、電磁波、スピン波、音波(フォノン)など多彩な波動制御を、3次元解析などで得られる計算設計結果に基づき、既存材料にナノからサブミクロンオーダのスケールで構造を導入することから工学的な応用が容易である利点を持つ。講演会では特に、光を操作する人工磁気格子(磁性フォトニック結晶)を用いたリアル3次元ディスプレイへの応用や、スピン波制御に活用してスピン波ロジック回路を実現しようとする取り組みなどについて紹介する。 | |||
| 第7回 | ロギール・アウテンボーガルト 氏 (「かみこや」代表、本学客員教授) |
里山と有用植物資源(こうぞ・みつまた)、建築素材としての和紙 | 2018/11/09 16:20–17:50 B107 |
| 【概要】新国立競技場の設計者である世界的建築家・隈研吾氏とのコラボ作品で著名な和紙作家・ロギール氏に、ものづくり哲学と里山の特質について語って頂きます。ロギール氏は、クリエイターであると同時に起業家の側面を有しており、梼原町に紙すき体験ができる宿泊施設「かみこや」を立ち上げ、有用植物資源の復興にゼロから取り組んだ経験もお持ちです。「かみこや」は海外客が多く体験型インバウンドの成功事例と言えます。その経験やアイディアについて学ぶことは、本講義のもう一つの目的であります。 | |||
| 第6回 | 大崎 章弘 氏 (お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンター 特任講師/科学コミュニケーター、元日本科学未来館スタッフ) |
科学コミュニケーション工学:科学と社会をつなぐ技術 | 2018/07/23 14:40–16:10 B106 |
| 【概要】専門家も非専門家も一緒になって創る未来の社会において、科学技術の担い手はどのようにして、専門的な知識を市民らと分かち合いながら一緒に活動することができるのでしょうか?科学と社会をつなぐ活動は「科学コミュニケーション」と呼ばれ、科学館、理科教育、メディアなど様々な分野において独自に発展を遂げています。演者はヒューマンインタフェースを専門としながら、工学的な観点から愛知万博での展示開発や、日本科学未来館の科学コミュニケーターとしての展示開発や対話手法、そして教材開発を中心に初等中等理科教育支援を実践的に研究してきました。本講演では科学と社会とをつなぐ技術と、その難しさを具体的な事例を交えて紹介します。 | |||
| 第5回 | 田中 秀和 博士 (YAMAKIN(株)主幹研究員、本学客員研究員) |
バイオセラミックスと最新の歯科材料開発 | 2018/07/19 10:30–12:00 C102 |
| 【概要】超高齢社会の到来による歯科医療ニーズの拡大と美容歯科,審美歯科といった見た目の美しさと機能性にこだわった治療の普及に伴い,歯科補綴物に使用される生体材料の重要性が増加しております.本講義では,生体材料の要件とその医療機器に関して,材料の選択とその特性を理解することを目的とし,歯科用途で主に使用されるガラスセラミックスやジルコニアの特徴を中心に紹介します. | |||
| 第4回 | 丹松 美由紀 氏 (鳥取大学技術部統括技術長) |
技術者の延長線上にあるもの -地域貢献・次世代へのバトン・充実感- | 2018/05/29 14:40–16:10 講堂 |
| 【概要】大学の理系学部には技術のスペシャリスト「技術職員」がいます.専門分野の技術をもち,教育・研究をサポートする技術職員には,地域の子どもたちの好奇心を刺激する“地域貢献”というもう一つの顔があります.これは大学などの教育機関だけではなく,これから皆さんの多くが就職する企業にも,社会的責任(CSR)として,立地地域の子どもたちへの教育支援者という顔があります.鳥取大学では,技術職員が鳥取県内の小中学生を対象とした「出前おもしろ実験室」を12年前から開催しています.東日本大震災後には,復興支援の一環として実験教室を現地で行いました.今回,大学の技術職員というポジションで何を考え,そして何ができたかについて,これまでの取り組みを中心に紹介します. | |||
| 第3回 | 市川 翼 博士 ((株)帝国データバンク 産業調査部副主任) |
企業ビッグデータから地域を支える企業を選ぶ | 2018/05/25 14:40– 講堂 |
| 【概要】地域を支える企業はどこか?2017年12月に経済産業省が公表した地域未来牽引企業2148社は、この問いに全国約150万社・500万超の取引からなる企業間取引ネットワークビッグデータを分析し、できるだけ客観的に答えようという試みの結果であった。本講演では、企業選定にあたって用いられた企業に関する定量データの性質や、データ分析の方針に加え、弊社での研究開発の取り組みをできるだけ平易な言葉で紹介する。選定された企業がどのような戦略をとっているのかなどもご紹介したい。 | |||
| 第2回 | 冨田 育義 博士 (東京工業大学教授) |
高い官能基耐性をもつアレン類のリビング配位分散重合の開発と応用 | 2018/05/18 10:30– K-HALL |
| 【概要】様々な官能基をもつモノマーに適応できるアレン類のリビング配位重合を開発するに至った経緯と基礎的な重合挙動を述べるとともに、本重合法を用いた材料科学的な応用として、特に精密な高分子ミクロスフェアやナノ構造体の合成と応用に関する研究を中心に紹介する。 | |||
| 第1回 | 藤田 武志 博士 (本学教授) |
金属材料の新展開 | 2018/05/15 14:40–16:10 講堂 |
| 【概要】世の中に金属材料であふれてていますが、脱合金化という手法で、金属材料はナノ先端材料への変わり、「元素戦略」から「二次元材料」に至る大きな横断的領域が広がっていることが明らかとなっています。本講演では、こうした金属材料(ナノポーラス金属)の概要と今後の展望についてお話します。 | |||
| 講演回 | 講演者 | 講演タイトル | 日時/場所 |
|---|---|---|---|
| 第10回 | 永野 正朗 氏 (グリーン・エネルギー研究所) |
FIT制度下における木質バイオマス発電の現状と宿毛バイオマス発電所のご紹介 | 2018/02/06 16:20– B107 |
| 【概要】2012年7月に再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)が導入されてから5年が経過した。FIT対象再エネ電源のひとつである木質バイオマス発電の現状と高知県宿毛市でバイオマス発電事業を運営する㈱グリーン・エネルギー研究所宿毛バイオマス発電所の事例を紹介する。 | |||
| 第9回 | 榎戸 輝揚 博士 (京都大学准教授) |
雷雲と雷の高エネルギー大気物理学 | 2018/01/30 10:30–12:00 B104 |
| 【概要】身近なはずの雷には、未だに新しい発見が溢れている。最近になって、雷雲や雷からエックス線やガンマ線といった高エネルギーの放射が見つかるようになってきた。日本でも冬になると北陸には強力な雷雲や雷が到来し、格好の観測対象になっている。学術系クラウドファンディングにサポートをもらい、雷が光核反応というエキゾチックな物理過程をもたらすことを発見するまでにいたるストーリーを紹介する。 | |||
| 第8回 | 飛 浩隆 氏 (SF作家) |
SF作家が考えたAIの三つの顔 | 2018/01/26 10:30–12:00 B104 |
| 【概要】パートタイム作家です。気がついてみるとここ四半世紀AIの登場するSF作品を書いてきました。「人間そっくり」なものもあれば、自然現象のようにままならないものまでさまざま。理工系の素養がないのでひたすら「文芸」の側からのアプローチですが、そこには「人や社会はどんなAIを欲望するのか」そして「AIは何を欲望するか」という作家の問題意識が反映されています。講義では自作に登場させたAIのさまざまな形をご紹介しながら、われわれの中に育ちつつある「21世紀の情感」を遠望します。 | |||
| 第7回 | 森本 幸司 博士 (理化学研究所専任研究員) |
新元素「ニホニウム」の発見 | 2017/12/12 14:40–16:10 C102 |
| 【概要】理化学研究所仁科加速器研究センターにおいて合成された113番元素は、国際機関グループは元素名"nihonium"(和名:ニホニウム)、元素記号"Nh"を提案し承認されました。本講義では、まず元素発見の歴史を最初に紹介し、ニホニウムの合成方法や使用した装置、観測結果について分かりやすく説明します。 また、現在準備を進めている119番および120番の新元素探索計画についても紹介する予定です。 |
|||
| 第6回 | 水上 元 博士 (高知県立牧野植物園園長) |
植物園と産業イノベーション | 2017/11/15 10:30–12:00 K101 |
| 【概要】植物園というと、多くの皆さんはチューリップやサルビアなどが四季折々に咲き誇っているフラワーガーデンをイメージされることと思います。しかし、植物園の本来の性格は植物研究を通じて産業振興に資する研究機関なのです。植物園が18世紀後半からはじまるヨーロッパ諸国の産業振興にどのように貢献してきたのかを歴史的に振り返りながら、今日の植物園の産業イノベーションへの貢献を牧野植物園の活動を例にとって紹介します。 | |||
| 第5回 | 坂本 猛 博士 (YAMAKIN株式会社) |
歯科用接着剤の研究と製品開発 -企業の研究開発をどのように楽しむか- | 2017/11/08 10:30–12:00 K101 |
| 【概要】接着という現象は、界面や被接着体などの機械的や化学的な要因が絡んで起こる現象です。そのような意味で接着剤の研究は、難解なパズルに取り組むようなものと言えます。ここに、製品化が加わると、科学だけではない検討や試行錯誤が加わるので、製品までの道のりが、まさしく険しい山を登るようだと言うことができます。 本講演では、接着剤の科学の紹介し、当社が最近開発した接着剤を例に、研究開発と製品化までの道のりもあわせて紹介します。製品開発は厳しい側面もありますが、難解なものに取り組む楽しさは、大げさですが、何物にも換え難いことを少しでもお伝えすること事ができれば良いなと思っています。 |
|||
| 第4回 | 木川 栄一 博士 (国立研究開発法人海洋研究開発機構 海底資源開発センター長) |
海底資源はどのように生成されるか | 2017/11/01 10:30–12:00 K101 |
| 【概要】近年、多くの注目を集めているメタンハイドレート、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、レアアース泥、マンガン団塊について、これらの海底資源がどのように生成するかについて、基礎から最近の研究成果までわかりやすく解説いたします。 | |||
| 第3回 | 山本 佳世子 博士 (日刊工業新聞社) |
スペシャリストでゼネラリスト | 2017/10/18 10:30–12:00 K101 |
| 【概要】科学技術の専門教育という強みを「スペシャリスト」として生かす。同時に、多様な分野や専門を融合して社会の豊かさを築く「ゼネラリスト」になる。その二つの視点が理工系人材にも求められるようになっている。科学技術と大学の専門記者をする講師が題材を提供し、研究の専門家と社会のコミュニケーションや、科学技術に関わるキャリアのポイントを、ともに考えていく。 | |||
| 第2回 | 酒井 泰斗 氏 (ルーマン・フォーラム) |
技術の社会学 | 2017/05/27 14:40– C101 |
| 【概要】理工学を学んだ学生は、就業後どのような問題に遭遇することになるのでしょうか。技術哲学、工学倫理、科学社会学、科学技術社会論などを手がかりにして考えてみたいと思います。 | |||
| 第1回 | 杉田 歩 博士 (大阪市立大学准教授) |
ボードゲームと人工知能 | 2017/05/23 14:40– C101 |
| 【概要】チェスをはじめとするボードゲームはかつては知性の象徴と考えられており、ボードゲームで人間に勝つプログラムの開発は、コンピュータの黎明期から人工知能研究の大きな目標でした。そしてコンピュータチェスは20世紀中に人間のトッププレイヤーに勝ち、その後、チェスよりはるかに難しいと言われていた将棋や、最難関と思われていた囲碁においてもコンピュータは人間を越えつつあります。この講演では、コンピュータ将棋を中心として、様々なボードゲームにおける人工知能の仕組みや最近の発展、今後の展望についてお話します。 | |||
| 講演回 | 講演者 | 講演タイトル | 日時/場所 |
|---|---|---|---|
| 第10回 | 永野 正展 博士 (本学特任教授) |
枯れない油田構想の社会実装 | 2017/01/27 16:20–17:50 C102 |
| 【概要】 研究成果の社会実装(事業化)事例の紹介。 人為的に再生可能な森林資源を用いた価値創造による地域の活性化を実現して行くプロセスを具体的に解説します。 キーワードは、環境・エネルギー・価値創造・起業・持続可能・地域再生・社会システム。 ●講演者情報 http://www.kochi-tech.ac.jp/kut/about_KUT/faculty_members/prof/nagano-masanobu.html https://sangakukan.jp/journal/center_contents/author_profile/nagano-m.html |
|||
| 第9回 | 山崎 義弘 博士 (早稲田大学教授) |
サッカーを科学する | 2017/01/24 14:40–16:10 C102 |
| 【概要】光電子的測定技術の進歩とコンピュータの進歩、そしてビッグデータを扱うネットワークサイエンスの進展があいまって、スポーツに「科学」のメスを入れることが可能となってきました。今回のお話では、非線形力学系物理学の視点からサッカー・ゲームを解析する試みを紹介します。果たして科学はサッカーの勝利を呼び寄せる手段となるのでしょうか。 | |||
| 第8回 | 藤崎 弘士 博士 (日本医科大学准教授) |
複雑な分子はどんな道筋でどれくらい速く反応するのか? -生体分子の構造変化とレアイベント- | 2016/12/16 14:40– C101 |
| 【概要】タンパク質はアミノ酸が連なってできる巨大で複雑な分子であり、分子間の相互作用によって美しい立体的な3次元構造を作る。その構造に応じて、生体内で様々な働きをするので、構造と機能の関係を理解することは生物学的には最も基本的であり重要である。ただし、生体分子が機能する際には、構造は固定されておらず、構造は局所的もしくは大域的に変化する。その変化は人間の感覚で考えると速いが、分子の立場で考えると非常に遅いプロセスであり、「レアイベント」と呼ばれるものになっている。本講演では、生体分子に関する一般的な導入から始めて、このレアイベントを考えるための理論的な手法について解説する。 | |||
| 第7回 | 岡田 仁志 博士 (国立情報学研究所准教授) |
貨幣が消える日:仮想通貨が拓く未来の経済 | 2016/11/10 14:40– C101 |
| 【概要】聞き所
(1)情報・数学の観点からも面白くわかりやすい 話題の仮想通貨の仕組みについて、非常にわかりやすく解説してくれる。 (2)世界史の観点からの解説もある 貨幣の成り立ちから、貨幣の歴史的変遷を2次元図にマッピングしながら、仮想通貨の歴史的意味について解説して下さいます。 |
|||
| 第6回 | 渡邊 高志 博士 (熊本大学教授) 谷口 ももよ 氏 (東洋美食薬膳協会代表理事) |
医食農連携の最前線:アグロメディカルフーズから薬膳まで | 2016/10/06 13:00–14:30 K-HALL |
| 【概要】熊本大教授と売れっ子薬膳料理家による、リレー講演会。食の高付加価値化には「知の流通」が不可欠です。医食農連携の観点から、バズワード「アグロメディカルフーズ、薬膳」に関連した事業展開の最前線をお伝えします。その後、本学主催の食のキャラバンとの関連を紹介したのちに、パネルディスカッションを行います。
●タイムスケジュール ★1st speaker(30分):渡邊先生(Agromedicine事業の最新状況、公開できる範囲で) ★2nd speaker(30分):谷口先生(薬膳の基礎概念+現在の事業内容) ★古沢が食キャラとの関連を補足(10分) ★パネルディスカッション(20分) ●講演者情報 渡邊高志教授(熊本大学) http://www.pharm.kumamoto-u.ac.jp/Labs/eco-frontier/aboutus/ 谷口ももよ先生(東洋美食薬膳協会 代表理事) http://www.yakuzen-salon.com/profile/index.html https://www.facebook.com/momoyo.taniguchi.1 |
|||
| 第5回 | 山下 慎吾 博士 (魚と山の空間生態研究所所長) |
景観生態学の視点で四万十川流域をみる | 2016/07/29 16:20– B106 |
| 【概要】四万十川流域など幡多地域でおこなわれている自然再生事業を紹介するとともに,文化的景観にもふれる内容です。 | |||
| 第4回 | 山内 尚雄 博士 (東京工業大学名誉教授、本学客員教授) |
「リニア中央新幹線」を支える力?超伝導現象 | 2016/07/12 10:30– B106 |
| 【概要】2045(2037?)年に開業し、東京-大阪間を67分で結ぶことをめざす「リニア中央新幹線」の東京-名古屋間の工事は、すでに2014年に着工されている。この近未来「鉄道」は18世紀後半以来の「一次産業革命」を支えてきた従来の鉄道とは画期的に異なる物理現象である「超伝導」を応用することにより実現できる。
超伝導現象は 20 世紀初めにオランダで発見されたが、その現象の原理解明はようやくその半世紀後になされた。その描像は奇異なもので、当時の人々の常識を破った理論体系として確立されたばかりの量子論を用いてなされた。一方、原理解明以前から、超伝導現象応用への努力は地道に行われてきていた。とくに、発見者である H. Kamerlingh-Onnes 自身が目指した強力な「超伝導電磁石」の開発は、彼の死後 40 年以上経った 1960 年代になって実現され、超伝導実用化の糸口となった。そのころわが国では、超伝導電磁石による「磁気浮上式鉄道」の開発と商業化への研究が始められ、今日では前述したように「リニア中央新幹線」の着工に至っている。 本講義では、超伝導現象とその熱力学的・微視的描像の解説、および超伝導現象を発現する物質、すなわち「超伝導体」の物性について紹介する。また、 1980 年代後半に勃発し、20 世紀末頃まで続いた「高温超伝導フィーバー」の体験と現状について述べる。さらに、さまざまな応用の可能性についても言及する。 |
|||
| 第3回 | 北川 宏 博士 (京都大学教授) |
現代の錬金術:人工的にパラジウムは作れるか | 2016/06/16 10:30– 講堂 |
| 【概要】卑金属から貴金属を創ろうとした中世の錬金術は現代化学の基礎をなしています。Alchemy(錬金術)はChemistry(化学)の語源になっています。本講演では、現代の科学技術を持ってして錬金術が可能かどうかについて解説を行います。また、化学結合の本質についても言及します。 | |||
| 第2回 | 須藤 靖 博士 (東京大学教授) |
一般相対論100年:重力波の直接検出 | 2016/05/17 16:20– 講堂 |
| 【概要】– | |||
| 第1回 | 三宅 淳 博士 (大阪大学教授) |
ディープラーニングが解く世界 | 2016/04/19 16:20– 講堂 |
| 【概要】深層学習=Deep Learningの応用としては車の自動運転などがよく取り上げられますが、もっと幅広く人の生活全般に影響を与えるでしょう。我々の研究グループでは、(a) バイオ応用として、DNAレベルの進化、タンパク質の突然変異や細胞の分化誘導、細胞内の遺伝子や化学反応の連鎖(例えばガン化メカニズム)、(b) 知能と運動の研究として、ロボットと人間の認識共有、テロリストの検知・人間の行動解析、などを行っています。今後医療技術や、社会的な予測技術、産業製造技術、自動翻訳などへ発展することは確実であり、それらの可能性や方向についてもお話したいと思います。 | |||
| 講演回 | 講演者 | 講演タイトル | 日時/場所 |
|---|---|---|---|
| 第14回 | 大政 謙次 博士 (東京大学教授) |
植物機能のリモートセン シング -細胞から植生へ、2次元から3次元へ- | 2016/01/08 14:40–16:10 C103 |
| 【概要】植物は、種や器官によって異なる特徴ある3次元空間構造をもち、また、その機能は、環境との相互作用で、空間的に異なっている。蒸散や光合成、成長といった基本的な生命活動に関係する機能も、この空間的構造の影響を受ける。このため、植物計測の分野では、細胞レベルあるいは器官レベルの状態を、生育環境を破壊することなく、2次元、さらには3次元的に計測する手法の開発が行われてきた。航空機や人工衛星からの広域リモートセンシングでも、地球観測研究の発達によって、より多くの植物機能に関する情報を得るための研究が盛んに行われている。ここでは、筆者らが行ってきた可視・近赤外分光反射、熱赤外、クロロフィル蛍光、距離ライダーなどの画像計測・リモートセンシング研究について、細胞から植生へ、2次元から3次元への視点で簡単に紹介するとともに、リモートセンシングによって植物機能に関する情報を取得する際の幾つかの問題点について述べる。文献などの詳細については、下記のサイトを参照されたい。
(研究論文)http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/joho/Omasa/papers2010311.html (著書・解説)http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/joho/Omasa/books20090123.html [HP] |
|||
| 第13回 | 上條 良夫 博士 (本学准教授) |
ゲーム理論の射程 | 2016/01/05 16:20–17:50 C103 |
| 【概要】本講義では、社会科学において必要不可欠となったゲーム理論の概略とその応用範囲について解説します。講義の導入では、じゃんけんを題材として、ゲーム理論的に考えることの難しさと面白さについて体感して頂きます。そこから得られた簡単な洞察を膨らませることで、戦略的不確実性を緩和させるような仕組みをゲーム理論が提案できることを説明します。具体的な事例としてインターネットオークションや Google などが実施している検索結果連動型広告のオークションに関する研究を紹介します。
[講演資料] |
|||
| 第12回 | 蒲池 雄介 博士 (本学教授) |
小型魚類を利用した胚発生の研究で何がわかるのか? | 2015/12/18 16:20–17:50 C103 |
| 【概要】胚発生の過程で、一つの細胞である受精卵から、どのようにして脳の細胞や眼の細胞が作られ、生理的な機能を持つ組織・器官が生じるのだろう か。現在の発生生物学では、分子生物学、細胞生物学、ゲノム生物学などの手法を総動員して、これらの問題に対してアプローチしている。本講演では、筆者らの「胚発生過程における遺伝子の発現制御に関する研究」とともに、なぜゼブラフィッシュなどの小型魚類が脊椎動物の胚発生の研究で重宝されるのかも紹介したい。
[講演資料(学内からのみアクセス可)] |
|||
| 第11回 | 小谷 浩示 博士 (本学教授) |
気候変動と資源環境問題:資本主義に持続可能性はあるのか? | 2015/12/11 16:20– C103 |
| 【概要】資本主義とは何か、資本主義社会に生きる我々はどの様な社会指向性を持つに至ったのか、を説明します。また、資本主義下で生きる我々は環境問題、生物多様性の喪失、気候変動問題等を解決出来るのか、それとも悪化させてしまうのか、これまでの経済実験結果を元に説明致します。結論として、競争により現世代の効率性を高める事の対価として持続可能性が危い事、そして持続可能性を高める為には環境技術の進化と資本主義に加えて更に新しい「何か」が必要であるかもしれない、という事を議論します。 | |||
| 第10回 | 山内 尚雄 博士 (東京工業大学名誉教授、本学客員教授) |
文明を推進してきた材料 | 2015/12/07 10:30– B107 |
| 【概要】– | |||
| 第9回 | 小林 豊 博士 (本学准教授) |
社会生物学から人類進化の理論へ | 2015/11/30 16:20– C102 |
| 【概要】社会問題・社会現象を分析する学問には、社会心理学、経済学、社会学などがあり、これらは社会科学と総称されます。しかしながら、人は生物である以上、他の動物と同様、自然淘汰によって進化してきたはずであり、人間社会を理解するうえで、生物学的な視点は欠かせないはずです。動物の社会行動の進化を研究する学問は、社会生物学と呼ばれ、進化ゲーム理論、包括適応度理論、集団遺伝学などの、厳密な数理モデルに基づく大変円熟した理論体系を持っています。理論的にはほぼ完成した学問であると言って良いでしょう。それに対し、人類進化の理論はあいまいでつかみどころがなく、完成とは程遠い状況にありますが、それが同時に魅力ともなっています。本講演では、社会生物学の基礎から始め、統一的なヒト進化理論の有力候補である二重継承理論を紹介し、進化論的な観点からヒトの特異性について議論します。 | |||
| 第8回 | 藤田 陽師 博士 (高知工業高等専門学校准教授) |
化学メーカーにおける計算化学的手法の適用例 | 2015/11/24 8:50–10:20 C103 |
| 【概要】量子化学計算、分子動力学計算に代表される計算化学的な研究手法は、化合物を提供し利益を得ることをその生業としている化合物製造業において一見必要のないように思われますが、上手く使えば、研究開発速度の加速し研究コストを低減することなどが可能です。
本講義では、ゼオライトを用いたフェノールの酸化反応の触媒系、ポリプロピレンの製造触媒系、および色素増感太陽電池における新規色素開発等における化学メーカーでの計算化学的手法の適用例を説明して下さいます。 |
|||
| 第7回 | 那須 清吾 博士 (本学教授) |
気候変動の影響予測と適応策 | 2015/11/05 16:20– C102 |
| 【概要】グローバルな気候変動の影響を特定の地域で予測し、適応策を検討し、地域において合意形成を行う為には、様々な学術分野を統合する必要がある。気象学、水文学、経済学、経営学などの学術分野による統合シミュレーションのプロセスを紹介するとともに、その成果に基づいて如何に適応していくの か、地域社会や行政との関わりにおいて考える。また、気候変動の影響が地域において非常に多様性があり、それが地理的、経済的な地域特性や、将来の社会経済シナリオによって生じる仕組みについても解説する。 | |||
| 第6回 | 木川 栄一 博士 (海洋研究開発機構 海底資源開発センター長) |
海底資源の生成と地球環境 | 2015/10/23 16:20– B108 |
| 【概要】最近話題になっている海底資源の概要を解説するとともに、その生成と地球環境の関係について、特に在来型の石油・天然ガス、コバルトリッチクラストの生成時の環境について最新の研究結果を紹介する。 | |||
| 第5回 | 山下 慎吾 博士 (魚と山の空間生態研究所所長) |
景観保全の実際 | 2015/10/ 15 16:30– C102 |
| 【概要】景観とは、みための景色ではなく、異なる生態系(景観要素)がモザイク状に分布する空間の全体的なシステムです。そして、そこに暮らす人々の生業を成り立たせている基盤でもあります。ここでは、文化的景観や自然再生といった概念をもとに、景観を保全していこうとする実際の動きについて紹介していきます。
高知新聞に不定期でコラムを執筆されてます。下記記事も参照。 [http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=332543&nwIW=1&nwVt=knd] 文化的景観に関する予備知識としては以下のリンクを参照。 [http://www.nabunken.go.jp/org/bunka/landscape/shimanto.html] |
|||
| 第4回 | 羽田野 直道 博士 (東京大学准教授) |
複雑ネットワーク:統計物理学の視点 | 2015/10/15 13:00– C103 |
| 【概要】この講演では、複雑ネットワークを概観し、統計物理学の視点からの解析について議論します。ネットワークとは、数学ではグラフと呼び、幾つかの点(ノード)を幾つかの線(リンク)で結んだものです。 数学的に主に研究されてきたのは、点をランダムに結んだランダムネットワークです。ところが、生体内のタンパク質の相互作用ネットワークから、人間社会の知人関係ネットワークに至るまで、様々な場面で現れるネットワークが、ランダムネットワークとは全く異なる統計的性質を持つことが最近、明らかになってきました。それらを総称して複雑ネットワークと呼びます。最大の特徴がスモールワールド性とスケールフリー性です。スモールワールド性とは、ネットワーク上の任意の2点を結ぶ最短経路が、ランダムネットワークからの予想よりもずっと短いという性質です。スケールフリー性とは、ノードに繋がるリンク数の頻度分布が冪分布であるという性質です。他にほとんど繋がっていないノードが非常に多数ある一方、いくらでも大量のリンクを抱えたノードも存在し、典型的なリンク数が存在しません。ランダムネットワークならポアソン分布になるところです。このような性質を持つネットワークがどのように現れるのか、また、そのようなネットワーク上でのモデルが、格子上とどのように異なる振る舞いをするのかが分野横断的に盛んに研究されています。これらを初歩から丁寧に説き起こしてお話しします。 | |||
| 第3回 | 西條 辰義 博士 (一橋大学教授) |
フューチャー・デザイン -七世代先を見据えた社会の構築を目指して- | 2015/06/02 16:20–17:50 講堂 |
| 【概要】市場制は人々の短期的な欲望を実現する非常に優秀な仕組みではあるものの,将来世代を考慮に入れて資源配分をする仕組みではない.一方,市場制を補うはずの民主制も現世代の利益を実現する仕組みであり,将来世代を取り込む仕組みではない.さらには,ヒトそのものも自己の生存確率を高めるために,過去のいやなことは忘れ,今の快楽を求め,将来を楽観的に考えるように進化した可能性が大である.このように将来世代の様々な資源を「惜しみなく奪っている」のが現世代である.これらに対処するために,存在しない将来世代に代わって仮想将来世代を現世代に導入し,持続可能性を含む新たな社会を創造する枠組みが「フューチャー・デザイン」である(マニフェストとして『フューチャー・デザイン』西條編著,勁草,2015,参照).
仮想将来世代を現代に導入する手法は,理論,実験,実践の分野でテイクオフしようとしている.崩壊しつつある全国の水道事業(更新するのに百年以上)においてフューチャー・デザインの手法を導入し,仮想将来世代と現世代との交渉で将来のデザインに成功しつつある岩手県矢巾町などの事例がある.復興庁終了後の新たな政府機関として将来省の提案も考えている.また,被験者を用いる実験では,仮想将来世代は,現世代とは全く異なった柔軟でしかも独創的な思考をすることも発見しつつある.気候変動を含む人類の存亡にかかわるテッピング・ポイントが迫りつつある現在,将来世代を考慮に入れた社会の仕組みのデザインは緊急の課題である. [講演資料] |
|||
| 第2回 | 稲葉 振一郎 氏 (明治学院大学教授) |
宇宙倫理学の試み | 2015/05/18 16:20–17:50 講堂 |
| 【概要】人類が宇宙空間に進出する近未来を想定すれば、そのとき人類が直面する課題は、必ずしも技術的なものばかりではない。地球周回軌道をこえた深宇宙進出には、そこで人間に伴っていると予想される知能ロボットと人間の関係や、人間社会自体の新たなありようの構築がその前提となるだろう。さらにそのとき、自己改造でエンハンスト・ヒューマンと化する術を身につけた我々は、知性とは何か、そもそも人間とは何か、という根源的問いに今一度直面するはずである。宇宙工学、ロボット工学、哲学、倫理学の交差する地点に見出される問題群を、SF小説やSF漫画を「実験事例」として取り上げながら探っていく。
[講演資料] |
|||
| 第1回 | 筒井 泉 博士 (高エネルギー加速器研究機構准教授) |
量子力学と時間反転 | 2015/05/07 14:40–16:10 C102 |
| 【概要】自然界に起きる様々な現象を、撮影したフィルムを逆回しにするように、時間を逆向きにさかのぼって眺めることができたら、その映像は奇妙に見えるだろうか。もし奇妙に見えるなら、それは我々の世界の時間の発展が、一定の方向に定まっているからだろう。そしてもしそうでなければ、仮に時間が逆行していても我々には気づかないから、時間の進行方向はどちらでも構わないことになる。我々人間が親しんでいるマクロな世界では、経験上、時間は逆行しないように見える。「覆水盆に返らず」である。しかしニュートンの古典力学において、1個の粒子の運動などの個々の物理現象に注目すると、それらは時間が逆行していても、我々には区別がつかないこと知られている。すなわち、少なくとも個々の物理系には、時間反転の対称性が存在するのである。同じことは、ハイゼンベルクらの量子力学でも成り立ち、やはり個々の量子現象は時間反転に対して対称である。ところが量子力学には古典力学には無かった「位相」という要素があるために、時間反転が粒子の電荷の符号を変え、粒子と反粒子を関係づける。さらに最近になって、量子力学における「弱値」という新しい物理量を眺めることにより、時間が順行と逆行を同時に行っているような場面に遭遇することが分かってきた。この講演では、このような時間の反転に関する興味深い最新の研究結果を、古典力学から量子力学、そして「弱値」の話へと導きながらやさしく解説する。
[講演資料] |
|||
| 講演回 | 講演者 | 講演タイトル | 日時/場所 |
|---|---|---|---|
| 第12回 | 山内 尚雄 博士 (東京工業大学名誉教授、本学客員教授) |
ヒトとモノ | 2015/01/26 10:40–12:10 K101 |
| 【概要】ヒト一人当たりのエコロジカル・フットプリント(EF)は、すでに1980年代に地球の生物生産力を上回るオーバーシュート状態に入っているといわれています。また全地球上の人口は急増しており、2050年には90億人を突破すると予測されています。すなわちヒトにとって「持続可能な」地球環境は、「限界」にきています。二足歩行し、両手が自由につかえ、個体間の高度なコニュニケーション能力をもったヒト(猿人)という動物が、アフリカに出現したのが、約600万年前と考えられています。爾来、ヒトは生物学的進化をとげるとともに、身の回りの自然物を「道具」とし、様々な「モノ」を造り、さらに高次のモノを次々に創製し、環境の変化に対応することにより「進化」して現在に至っています。その道筋で、「火の使用」を始めたのは画期的な出来事でした。こうして造った様々なモノを用いてヒトが地球上に生活している状態を「文化」とか「文明」と呼んでいます。最近の科学的な人類学や考古学、はたまた歴史学は、文明はヒトとモノとの不断の共鳴的展開により各種の環境変化に対応して生き長らえてきたことを、明らかにしつつあります。
ヒトにとって、モノとは、素材=自然物に始まり、素材を加工したり組み合わせたりした道具やデバイス、機器、装置、施設などのすべての「人工物」をさします。しかし、突然どこか外部からヒト自身が開発したのではない高次のモノが与えられてもヒトには何の役にも立ちません。ヒトとモノの間のコトと呼ぶべき経験やソフト、マニュアルなどの「科学技術」を含む知識全般が不可欠です。すなわち、「材料技術・科学」の正体はモノではなくコトです。自然物である素材だけでなく、人工物に関するコトです。人類史をふりかえると、「新材料」が新しいモノを生み出し、文明のパラダイム・シフトを生じせしめてきたことは大変興味深い事実です。 本講義では、人類史上不可欠な新材料の出現と、それに伴う材料技術・科学の進展が文明のパラダイム・シフトを誘起する様を概観することにより、限界に近いグローバル化した現代文明の持続に貢献する材料技術・科学というコトについても一考したい。 |
|||
| 第11回 | 江守 正多 博士 (国立環境研究所気候変動リスク評価研究室長) |
気候変動リスクと人類の選択 | 2015/01/09 14:50–16:20 C102 |
| 【概要】人間活動に伴う温室効果ガスの排出による気候変動(地球温暖化)が進んでいます。その危険な影響を避けるため、世界平均気温の上昇を産業革命前を基準に2℃未満に抑えることが国際社会の目標とされています。しかし、その実現のためには今世紀末に世界の温室効果ガス排出量をほぼゼロにする必要があります。この途方もない課題に人類はどう向き合えばよいのかを論じます。 | |||
| 第10回 | 渡邉 高志 博士 (本学教授) |
エキゾティックな植物のお話 | 2014/12/24 14:50–16:20 C101 |
| 【概要】– | |||
| 第9回 | 下村 政嗣 博士 (千歳科学技術大学教授) |
古くて新しい、バイオミメティクス(生物模倣) | 2014/12/19 14:50–16:20 C102 |
| 【概要】生物に学ぶ、という考え方は古くからあります。ナイロンやマジックテープはその代表例です。今世紀になって、欧米を中心にバイオミメティクスの新しい潮流がおこっています。ドイツは、国際標準化の提案をしてきました。アメリカでは環境やエネルギー問題の救世主とも言われています。生物模倣技術の現代的な意義とそれがもたらす技術革新について説明します。 | |||
| 第8回 | 大槻 久 博士 (総合研究大学院大学助教) |
理論で切り込む社会生物学 | 2014/12/10 13:10–14:20 C102 |
| 【概要】社会生物学とは、個体同士が集まってある種の調和的な集まり、すなわち「社会」を作る生物に関する学問です。例えばアリやハチなどの社会性昆虫のコロニー、サカナの群れ、ライオンの群れなどはその一例です。社会を作れば、個体単独では成し得ないことを協力によって達成でき(例えば大きなハチの巣などはその良い例でしょう)、結果としてより多くの子孫を残すことができるので、社会が出来上がること自体は一見すると進化理論には何ら矛盾しないように思えます。
しかし、進化は集団レベルに働くものではなく、個体レベルに働くものです。言い換えれば、各個体は社会を構成する一員であるものの、その中において他者よりもなるべく多くの子孫を残そうと競争し合う存在です。したがって、一見すると「調和的」に出来上がっているような生物の社会も、実は個体間の軋轢と葛藤の結果として出来上がっている場合が往々にしてあります。 私の専門分野は「数理生物学」と言って、数学やコンピュータなどの方法を用いて、様々な生命現象に働く原理・原則を解き明かそうとする分野です。今回は社会生物学における複数の例を通して、理論がどのような問題をどのように解決していくかを紹介し、たぶん皆さんが初めて耳にするであろう「数理生物学」の研究の一端をご紹介できればと思います。 |
|||
| 第7回 | 宮崎 州正 博士 (名古屋大学理学部教授) |
やわらかいモノの理論物理学 | 2014/12/02 16:30–18:00 B106 |
| 【概要】理論物理学というと、とてつもなく小さな原子や素粒子の世界や、とてつもなくはるか彼方の宇宙やビッグバンの世界が、研究の対象だと思っていませんか。身の回りのありふれた自然現象は、ニュートンの時代に全部解決してしまっていて、物理のフロンティアは極大の宇宙と極小の素粒子にしか残っていないと思っていませんか。それは大変な誤解です。「液体は流れるが、固体は動かない」というあまりにも当たり前の事実すら、最先端の理論物理学は説明できないのです。身近な現象にも未解決問題が残っている、というのは不適切な言い方です。身近な現象のことを我々人類は何も理解していないというほうが正しいのです。私の専門は、「ソフトマター物理学」です。文字通り、「やわらかい物質」が研究対象です。蜂蜜やマヨネーズ、歯磨き粉やクリームは、液体でしょうか、固体でしょうか。こんな身近な物質を理解することが、我々の知識の地平線をどんなふうに広げていくのかについて、分かりやすく説明する予定です。 | |||
| 第6回 | 須藤 靖 博士 (東京大学理学部教授) |
世界は法則に支配されているか | 2014/11/12 16:30–18:00 C102 |
| 【概要】宇宙の起源、生命の起源、意識の起源は、科学が解明すべき究極の難問の代表的なものである。しかしながら、これらはまだ解明されているというにはほど遠いし、そもそも我々人類の知性のレベルで理解できるかどうかすらわからない。
その一方で、より身近な世界(特に無生物的現象)に関しては、その振る舞いは驚くべき精度で説明に成功している。これは、いったん初期条件が与えられれば、その後の振る舞いは基本的には物理法則にしたがっているからである。 むろん、このような素朴な決定論的世界観には限界がある。量子論的な不確定性、さらには決定論的であるにもかかわらず系を特徴付けるパラメータに対する強い依存性のために、未来を予言することは不可能なことも多い。にもかかわらず、全体としてこの世界は法則にしたがって、ある程度必然的に進化しているように思われる。 その具体的な例は、誕生して38万年後の宇宙の「初期条件」ともいえる宇宙マイクロ波背景輻射温度地図が予言する現在の宇宙の姿が観測データと驚くべき一致を示していることである。 この宇宙地図の鑑賞法を理解すれば、世界が法則にしたがっているという世界観に共感してもらえるのではなかろうか。とすれば、生命と意識は、我々が具体的な説明に成功するかどうかは別として、この宇宙の進化の必然的な帰結であると予想できる。一方、では宇宙はなぜ誕生したのか。これは、宇宙の誕生以前に法則は存在したのか、というかなり哲学的な問いかけそのものであり、あいまいな言い方ではあるものの、必然ではなく偶然を持ち出さざるを得ないように思われる。 今回は、宇宙論と太陽系外惑星の研究を具体的な例として取り上げながら、物理学的世界観の成功と限界に関して、かなり個人的な(したがって正しいかどうかはまったくわからない)見解を紹介してみたい。 |
|||
| 第5回 | 木川 栄一 博士 (海洋研究開発機構海底資源開発センター長) |
海底資源を探る | 2014/10/20 13:10–14:40 C102 |
| 【概要】日本近海に賦存する金属鉱物資源(海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース泥)について、我が国における開発の現状及び最先端の研究についてわかりやすく解説いたします。また、本年度より開始された現政権の重要施策「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の採択課題である「次世代海洋資源調査技術」についてのご紹介もいたします。 | |||
| 第4回 | 関根 良紹 氏 (相転移プロダクション) |
科学と社会の狭間の一市民の奮闘 | 2014/10/15 16:30–18:00 C102 |
| 【概要】近年科学と社会の関係がやたらと取り沙汰されているが社会的に論じられていることは私にとってはどうでもいい.私から見て決定的に重要なのは社会の中の個人がどう生きていくかであり,数学や自然科学を学んできた者達がその専門への愛情を捨てるように強要されることなく生を謳歌できるかでありいかにしてそれらと添い遂げていくかだ.一昔前ならいざ知らず,今はたとえどれだけ強く願ったところで皆が皆大学や企業,研究所の研究者・開発者になれるわけでもない.そんな中,大学・大学院で専門教育を受けた個人が何をしてどう生きていくか,どう社会と殴り合っていくのか,研究開発には従事していない一個人の立場からその戦いの一例を見せたい.
[講演資料] [映像記録] |
|||
| 第3回 | 島 明日香 博士 (宇宙航空研究開発機構未踏技術研究センター研究員) |
有人宇宙活動を支える生命維持技術について | 2014/07/10 10:40–12:10 K-HALL |
| 【概要】人間を地球とまったく異なる宇宙環境で生かすには、実に様々な技術が必要です。今回のご講演ではJAXAの業務内容などを簡単に説明して頂いたのち、有人宇宙技術の具体例を、CO2からO2を作る循環型空気再生技術の研究を例に説明して下さいます。
また、宇宙機の設計などについても紹介して下さいますので、機械・電気・システム・情報系等の皆様も是非ご来聴下さい。 |
|||
| 第2回 | 新井 紀子 博士 (国立情報学研究所教授) |
ロボットは東大に入れるか | 2014/05/30 16:30–18:00 講堂 |
| 【概要】国立情報学研究所は2011年にグランドチャレンジプロジェクト「ロボットは東大に入れるか」を開始した。本プロジェクトは、1980年以降、情報検索・自然言語処理・画像処理・数式処理・証明支援システム等細分化された人工知能分野を再統合することで新たな地平を切り拓くことを目的に、発足したものである。本講演では、今「大学入試」を人工知能研究のターゲットとすることの意義とその理論的・技術的困難について概説した上で、2年間の研究成果を紹介したい。
[HP] |
|||
| 第1回 | 筒井 泉 博士 (高エネルギー加速器研究機構准教授) |
量子世界における実在とは:猫話二題 | 2014/05/23 16:30–18:00 講堂 |
| 【概要】量子の世界では常識的な実在像が成立せず、モノの存在や現象間の因果関係が曖昧になる。現代の自然科学を支える量子力学が教える不可解な自然界の姿について、最新の量子的実在性の研究の話題を含め、新旧の2匹の猫(シュレーディンガーの猫と量子チェシャ猫)の話を交えながらやさしく解説する。 | |||
| 講演回 | 講演者 | 講演タイトル | 日時/場所 |
|---|---|---|---|
| 第22回 | 小澤 正直 博士 (名古屋大学教授) |
不確定性原理の最前線 | 2014/01/22 14:50–16:20 C101 |
| 【概要】量子力学の代名詞でもある「ハイゼンベルクの不確定性原理」が小澤正直博士によって書き換えられた!いまからちょうど二年前に一般紙の一面トップでも伝えられたこのニュースを、覚えておられる方も多いのではないでしょうか。この基礎物理学の大発見を巡る事情を、このたび小澤博士ご自身から聞く事ができる希有の機会が与えられました。皆様のご来聴を歓迎いたします。
[HP] |
|||
| 第21回 | 高橋 泰城 博士 (北海道大学准教授) |
心理物理学的神経経済学とその社会科学への応用 | 2013/12/20 14:50–16:20 C102 |
| 【概要】近年発展が著しい「神経経済学」の分野において、心理物理学的理論の導入が大変有用であることが、我々の研究で明らかになってきた。時間割引やリスク下の意思決定を、心理物理学的神経経済学の枠組みを用いて定式化できることの紹介を行い、量子意思決定理論との関連や、(経済学や政治学などの)社会科学における問題への応用を解説する。 | |||
| 第20回 | 山内 尚雄 博士 (ヘルシンキ工科大学教授) |
ヒトとモノの共鳴的相関の展開 -材料技術・科学史 | 2013/12/19 10:40–12:10 C101 |
| 【概要】近年発展が著しい「神経経済学」の分野において、心理物理学的理論の導入が大変有用であることが、我々の研究で明らかになってきた。時間割引やリスク下の意思決定を、心理物理学的神経経済学の枠組みを用いて定式化できることの紹介を行い、量子意思決定理論との関連や、(経済学や政治学などの)社会科学における問題への応用を解説する。 | |||
| 第19回 | (事情により延期) | ||
| 【概要】– | |||
| 第18回 | 小野寺 健一 博士 (高知大学教授) |
生き物が創る物質を探し出す | 2013/11/28 13:10–14:40 C102 |
| 【概要】– | |||
| 第17回 | 木川 栄一 博士 (海洋研究開発機構) |
燃える氷、メタンハイドレート | 2013/11/06 14:50–16:20 C101 |
| 【概要】海中に眠る未開発の資源、メタンハイドレートについて、基礎からはじまって昨年以降の最新の成果を含めてお話いたします。 | |||
| 第16回 | 岡本 佳男 博士 (名古屋大学教授) |
多糖系HPLC用キラル充填剤の開発と応用 | 2013/10/24 17:15–18:00 K-HALL |
| 【概要】– | |||
| 第15回 | 大越 慎一 博士 (東京大学教授) |
磁気化学を基盤とした新機能ナノ構造物質のボトムアップ創製 | 2013/10/24 16:30–17:15 K-HALL |
| 【概要】– | |||
| 第14回 | 八島 栄次 博士 (名古屋大学教授) |
らせん高分子の合成と応用 | 2013/10/24 15:35–16:20 K-HALL |
| 【概要】– | |||
| 第13回 | 石田 康博 博士 (理化学研究所主任研究員) |
液晶の塩を使ったキラル極微フラスコの科学 | 2013/10/24 14:50–15:35 K-HALL |
| 【概要】– | |||
| 第12回 | 山田 眞二 博士 (お茶の水女子大学教授) |
カチオン-π相互作用を利用する有機合成 | 2013/10/24 13:55–14:40 K-HALL |
| 【概要】– | |||
| 第11回 | 井上 佳久 博士 (大阪大学教授) |
キラル超分子光化学 | 2013/10/24 13:10–13:55 K-HALL |
| 【概要】– | |||
| 第10回 | 中村 勝弘 博士 (トリノ工科大タシケント校教授) |
量子カオスとナノサイエンス | 2013/07/30 16:30–18:00 C102 |
| 【概要】カオスは、振り子の周期運動や太陽の周りの惑星のケプラー運動とは異なり、未来予想がまったく不可能な運動である。カオスは、ナノスケールの世界では特に重要なコンセプトである。たとえば、量子ドットに閉じ込められた電子の軌道運動や分子内の電子の運動は、ニュ-トン力学で考察するとカオスを示す。しかし、ナノスケールの世界では、「不確定性原理」が支配するのでカオスの兆候は ややかき消されてしまう。とはいえ、カオスは、開放系量子ドットにおける弱局在ピークのフラクタル構造やアルカリ原子ガスのシュタルク準位の複雑構造に頻繁に顔を出す。これを量子カオスという。この講演では、ナノサイエンスに関係する量子カオスの基礎を解説する。 | |||
| 第9回 | 鈴木 啓介 博士 (東京工業大学教授) |
ハイブリッド天然物に学ぶ:有機合成、一度やったらやめられない | 2013/07/19 17:15–18:00 K-HALL |
| 【概要】私達は天然有機化合物の多彩で美しい構造に魅せられ、合成研究を行ってきた。特に複数の生合成経路の交差から産生される複合構造を“ハイブリッド天然物”と呼び、その合成的諸問題を契機として新たな合成手法や合成戦略の開拓に向かうとともに、天然物合成の完成を目指してきた。本講演ではポリケチド系生合成の産物(多環式骨格)に糖質が複合化した構造を有する天然物群(アリール C-グリコシド)の合成研究、さらに偶然始まったポリフェノール系化合物の合成研究を紹介する。 | |||
| 第8回 | 山口 雅彦 博士 (東北大学教授) |
ラセン有機分子の合成と機能 | 2013/07/19 16:30–17:15 K-HALL |
| 【概要】ラセンは自然界で広く見られるキラル構造です。ところで、有機分子にもラセン構造をもつものが知られていますが、性質はわかっていません。ラセン構造の有機化合物を大量に供給することが容易でなかったためです。私たちはラセン多環芳香族化合物である光学活性ヘリセンの大量合成法を開発して誘導体を合成し、性質と機能を調べる研究を行っています。とくにラセン小分子の研究をもとに、ヘリセンを連結したラセン大分子、さらに自己集合体に物質ボトムアップするアプローチに興味を持っています。今回はこの例についてご紹介させていただきます。 | |||
| 第7回 | 立間 徹 博士 (東京大学教授) |
金属ナノ粒子による様々な光機能の創出 | 2013/07/19 15:35–16:20 K-HALL |
| 【概要】金属は光をよく反射しますが、ナノサイズにすると,吸収するようになります。この性質は,ステンドグラスの着色などに使われてきました。さらに工夫を加えることで,吸収した光のエネルギーを太陽電池や光触媒に利用できるようになります。また,当てた光の色を記憶する材料,目には見えない(赤外カメラでは見える)画像を表示できる材料,光で変形するポリマー材料などにも応用できます。こうした様々な機能と,その原理について紹介します。 | |||
| 第6回 | 宮山 勝 博士 (東京大学教授) |
次世代電池のための材料開発-リチウムを使わないプロトン電池とMg二次電池- | 2013/07/19 14:50–15:35 K-HALL |
| 【概要】リチウムイオン電池の高出力化や大型化の研究開発が進められているが、資源的制約や材料特性上の課題から限界が見えつつある。新たな電池の候補として、水溶液を電解質に用いた安全性の高いプロトン電池や、Mg2+などを可動イオンとして大容量が期待される多価カチオン二次電池がある。講演では、それらの動作原理、電極材料や特性、課題などを紹介する。 | |||
| 第5回 | 鈴木 勉 博士 (東京大学教授) |
RNAエピジェネティクスと生命現象 | 2013/07/19 13:55–14:40 K-HALL |
| 【概要】RNAは転写後に様々なプロセシングや修飾を受けて成熟し、はじめてその本来機能を発揮する。これまでに100種類を超えるRNA修飾が様々な生物から見つかっている。最近、遺伝子発現がRNA修飾によって制御されるという、RNAエピジェネティクスという概念が生まれつつある。また、RNA修飾の異常はヒトの疾患の原因になることが知られており、RNA修飾病という概念が定着しつつある。本講演では、最近私たちが発見した新規RNA修飾の構造と機能、RNA修飾病の発症メカニズムについて報告する。 | |||
| 第4回 | 和田 猛 博士 (東京理科大学教授) |
リン原子修飾核酸医薬の立体制御 | 2013/07/19 13:10–13:55 K-HALL |
| 【概要】近年、医学のめざましい進歩により、再生医療や遺伝子治療などの実用化にも道が開かれつつある。医薬品の開発に目を向けると、現在注目を集めている抗体医薬に続く次世代の医薬として、核酸医薬の実用化に大きな期待が寄せられている。核酸医薬の実用化において解決すべき課題は、核酸誘導体の生体内における安定性の向上とデリバリーである。我々は、これらの問題を克服するための手法の一つとして、核酸リン原子の化学修飾に着目して研究を行っている。核酸分解酵素は、DNAやRNAのリン酸ジエステル結合を加水分解する酵素であるから、ここに適切な化学修飾を施すことにより、高い分解酵素耐性を獲得することができる。また、水溶性の高いリン酸ジエステル結合の非架橋酸素原子を他の元素や置換基に変換することにより、脂溶性が向上し、細胞膜透過性を向上させることも可能である。しかし、核酸のリン原子に修飾を施すと、各リン酸ジエステル結合つき、2種類の立体異性体が生成し、立体異性体間で核酸類縁体の生体内における安定性や二重鎖形成能など、医薬としての性質に大きく異なるため、その立体制御は極めて重要な課題である。本講演では、核酸医薬として有用なホスホロチオエートDNAおよびRNAの立体選択的合成と、立体が制御されたH-ホスホネートDNAを経由する様々なリン原子修飾DNA類縁体の立体選択的合成について紹介する。 | |||
| 第3回 | 谷垣 実 博士 (京都大学原子炉実験所助教) |
GPS連動型放射線計測システムKURAMAの開発と運用~地域を見守る「目」~ | 2013/05/22 14:50–16:20 C102 |
| 【概要】2011年3月の東電福島第一原子力発電所事故により、東日本の広範囲で深刻な放射性物質による汚染が発生しました。この事故に対応するべく、京都大学原子炉実験所では2011年4月にKURAMA(Kyoto University RAdiation MApping system)を開発、福島県や文科省他が行った事故直後の汚染状況の迅速かつ詳細な調査に活用されました。その後KURAMAはKURAMA-IIへと進化し、100台以上のKURAMA-IIを一斉に稼働しての東日本全体の大規模調査が実施された他、生活圏の放射線量を継続的に監視する「地域を見守る目」としての活用が本格的に始まろうとしています。今回はKURAMAやKURAMA-IIのあらましや開発の経緯、現状や今後の展開などを福島の現状を交えながらお話します。
[HP] |
|||
| 第2回 | 飯田 圭 博士 (高知大学理学部教授) |
中性子星とパルサー | 2013/05/14 14:50–16:20 C102 |
| 【概要】中性子星は超新星爆発のあとに残るコンパクトな天体の一形態である。その一部は、星の回転とともに規則正しく電波パルスを送り続ける「パルサー」として見えている。その質量やサイズといった基本的な性質を知ることすら天文学においては全く容易なことではないが、公転運動に対する一般相対論の効果のおかげで、質量については精度よく決まる例がある。すると星を構成するきわめて高密な物質の性質を窺い知ることが可能となる。この例をはじめとして、中性子星に見られる多彩な現象から、地上では作り得ない超高密度物質の性質をさぐるという不思議な「実験」の一端を紹介する。
[HP] |
|||
| 第1回 | 菊池 豊 博士 (本学連携センター教授) |
小水力発電で地域を活性化 ~どうやって!?~ | 2013/05/08 14:50–16:20 C102 |
| 【概要】日本では中山間部で過疎化と高齢化が進行しています。衰退する地域社会を自立させる方法がいくつも考えられ実施されています。その中で私たちは、地域が主体となって再生可能エネルギー事業、それも小水力発電事業を実施することで地域を再生しようとしています。なぜ小水力発電なのか、どんな課題があってどう解決しようとしているのかをご紹介しようと思います。なお、これは出来上がっている話ではなく、work in progress なプロジェクトです。積極的な御意見を御待ちしています。
[講演資料PDF] [HP] |
|||